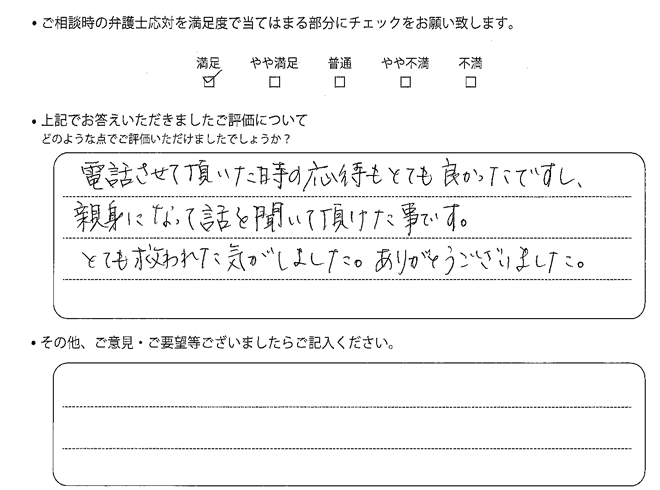交通事故による腰椎圧迫骨折の慰謝料相場は?後遺障害等級なども詳しく解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
腰椎圧迫骨折は、治療に時間がかかったり、手術を伴ったり、後遺症が残ったり等のおそれがある重い怪我のひとつです。特に高齢の方に生じやすく、相手方保険会社との交渉の際に持病や既往症との関係で争いになりやすい類型でもあります。 交通事故による腰椎圧迫骨折で適切な慰謝料を受け取るためには、正しく通院・検査をして後遺障害等級認定を受けることが重要です。 そこで本記事では、「交通事故による腰椎圧迫骨折」に着目し、腰椎圧迫骨折の慰謝料相場や後遺障害等級認定を受けるためのポイントなどについて、詳しく解説していきます。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0078-6009-3003
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
交通事故による腰椎圧迫骨折とは
腰椎圧迫骨折とは、“脊柱のうち腰に位置する椎骨(腰椎)に対して大きな衝撃が加わることにより、骨が圧迫されて椎体が潰れてしまう現象のこと”をいいます。特に上下の方向から強い力が加わることで、圧迫骨折が生じやすくなります。 そのため、次のような事故態様の場合は、腰椎圧迫骨折が生じやすいと考えられます。
- 交通事故で車両が大破するくらいの強い衝撃を受けた場合
- 自動車とバイク・自転車との接触事故で、バイク・自転車の運転者が路面に転倒した場合
- 自動車と歩行者との接触事故で転倒して、歩行者がしりもちをついた場合 など
このような場合は、腰椎圧迫骨折が生じやすい事故態様であるといえるため、直ちに病院を受診して適切な治療を行うようにしましょう。
腰椎圧迫骨折の症状
腰椎圧迫骨折の症状は、どの程度骨折したのかによって様々です。 椎体が事故による強い衝撃で潰れてしまうと、背骨が前方に傾き、異常姿勢(=猫背)が進行してしまいます。その結果、次のような症状を伴うことが多くあります。
- 骨折部位の痛み
- 腰や足など、下肢のしびれや麻痺
- 歩行困難 など
これらの症状は、骨折の程度が大きいほど、伴う可能性が高まります。 そのため、下肢のしびれ・麻痺や歩行困難などの症状が生じている場合は、事故によって腰椎圧迫骨折を負った可能性があると考え、早めに病院を受診することが大切です。
腰椎圧迫骨折の診断
腰椎圧迫骨折の診断は、まず問診・触診で痛みが発生している部位を確認し、レントゲンでその部位を特定していきます。レントゲンにて腰椎圧迫骨折が認められる場合は、さらにCT検査やMRI検査で骨や軟部組織の損傷の程度を確認します。 事故直後は痛みやしびれを感じず、後になって骨折していることが判明する場合も少なくありません。その場合、事故から時間が経過していることを理由に、事故と骨折との因果関係が疑われるおそれがあります。 そのため、事故直後に痛みやしびれなどの自覚症状が生じていない場合も、できるだけ早めに病院を受診することが大切です。「時間が経てば治るだろう」と考え、病院を受診しないと決断することはしないようにしましょう。
腰椎圧迫骨折の治療
腰椎圧迫骨折の治療は、安静にする、コルセットで固定するなどの「保存療法」が一般的です。 コルセットで痛みや変形の進行を防いだり、骨折の程度によってはギプスを使用することもあります。また、なかなか痛みがとれない場合には、「バルーン椎体形成術」といって、安定しない骨を固めて痛みを止めるために、椎体に骨セメントを入れて骨の内側から固定する手術が行われる場合もあります。 しかし、いずれの場合も骨折した椎体は潰れたまま骨癒合することになるため、基本的に椎体が元の状態に戻ることはきわめて少ないです。そのため、できるだけ元の状態に近いところまで戻して固定するという治療が行われます。
交通事故による腰椎圧迫骨折の慰謝料相場
交通事故における慰謝料には、下表のとおり、3つの算定基準があります。 このうち、弁護士基準がもっとも高い算定基準となりますが、弁護士基準での計算は「弁護士が示談交渉を行う際」に限られるのが実情です。
| 自賠責基準 | 自動車損害賠償保障法に基づく、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 任意保険会社ごとに算定基準を持っていて、非公開 |
| 弁護士基準 | 過去の裁判例をもとに設定された被害者が受け取るべき基準で最も高額になる |
なお、以下のページでは請求可能な賠償金額の目安を知ることができる【自動計算ツール】をご紹介しています。ぜひご参考になさってください。
腰椎圧迫骨折で請求できる慰謝料は、“入通院慰謝料”と“後遺障害慰謝料”の2つです。 では、それぞれの慰謝料について、次項にてもう少し掘り下げてみていきましょう。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、“事故が原因で負った怪我の治療のために、入院や通院を強いられたことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料”のことをいいます。 入通院慰謝料は、基本的に治療のために入院または通院した事実があれば、被害者側の損害として加害者側へ請求することができます。しかし、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のどの基準を用いるかによって、計算式が異なるため、請求できる金額に差が生じます。 たとえば、腰椎圧迫骨折で入院1ヶ月、通院6ヶ月の場合の入通院慰謝料の相場は、弁護士基準だと149万円ですが、自賠責基準はそれよりも低い金額になります。 詳しい計算方法については、以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、“事故が原因で負った怪我による後遺症で生じた精神的苦痛に対する慰謝料”のことをいいます。 後遺障害慰謝料は、「怪我の後遺症が事故によるもの」と認められる後遺障害等級認定を受けなければ、加害者側へ損害として請求することはできません。また、どの後遺障害等級に認定されたかによって後遺障害慰謝料の金額が異なります。 なお、後遺障害慰謝料も入通院慰謝料と同様に、用いる算定基準によって相場が異なります。 任意保険基準の内容は各保険会社によって独自に定められており、非公開であるため割愛しますが、下表のとおり、自賠責基準と弁護士基準を比較してみても金額に大きな差があることがわかります。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 6級 | 512万円(498万円) | 1,180万円 |
| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
| 14級 | 32万円(32万円) | 110万円 |
※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用
後遺障害に認定されたら逸失利益も請求できる
事故による怪我の後遺症が後遺障害として認定されると、後遺障害慰謝料だけでなく、“逸失利益”も被害者側の損害として加害者側に請求することができます。 後遺障害逸失利益とは、「事故に遭わなければ将来得ることができたはずの収入に対する補償」のことで、以下の計算式を用います。
<後遺障害逸失利益の計算式>
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
会社から給料が支給される給与所得者だけでなく、個人事業主はもちろんのこと、主婦・主夫や無職の方でも場合によっては後遺障害逸失利益を請求することができます。 後遺障害逸失利益について、詳しくは以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
腰椎圧迫骨折の後遺障害等級と認定基準
認定される後遺障害等級は、腰椎圧迫骨折で生じた骨折や後遺症の程度によって異なります。 「治療を終えても後遺症として残っている身体の障害がどのようなものなのか」が詳しく調査され、認められる障害に応じて後遺障害等級が認定されます。 腰椎圧迫骨折の後遺障害として代表的なものは、下表の4つと考えられています。
| 神経症状 | 神経の圧迫による、足のしびれ、痛み、筋力低下など |
|---|---|
| 運動障害 | 背骨の変形により、背中が曲がりにくくなるなど |
| 変形障害 | 背骨の変形による、見た目の変化 |
| 荷重機能障害 | 腰を支える機能が失われ、硬性補装具が必要となる |
では、それぞれの後遺障害について、もう少し掘り下げてみていきましょう。
①神経症状
腰椎圧迫骨折による神経症状とは、神経が圧迫されることで生じる「足のしびれや痛み、筋力低下」などを指します。 なお、神経症状で認定される可能性のある後遺障害等級は、12級13号と14級9号です。 神経症状は、目視、つまり、実際に目で見ることはできないことから、しびれや痛みの存在を画像所見などで明らかにしなければなりません。 そのため、神経症状が画像所見などから医学的に証明できる場合には12級13号が、画像所見はないものの、神経症状を医学的に説明できる場合には14級9号が認定になるとされています。
| 等級 | 基準 |
|---|---|
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
②運動障害
腰椎圧迫骨折による運動障害とは、背骨が変形することで「背中が曲がりにくくなる」などの障害が現れることを指します。 なお、運動障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、6級5号と8級2号です。 運動障害は、MRI検査などの画像所見や前屈・後屈といった運動をした際に「どれくらい背中を曲げることができるか」を測定し、その可動域を確認します。そして、確認した可動域の程度によって、いずれかの後遺障害等級が認定されます。可動域の程度が大きい場合には6級5号が認定となります。
| 等級 | 基準 |
|---|---|
| 6級5号 | 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの |
| 8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
③変形障害
腰椎圧迫骨折による変形障害とは、背骨が変形して骨癒合したために、「見た目が変化する」ことを指します。 なお、変形障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、6級5号、8級相当、11級7号です。 変形障害は、画像所見で背骨の変形が確認できることはもちろん、可動域や側弯度の程度など、認定にあたり細かい基準が設けられています。そのため、変形障害を立証するために必要な検査をすべて受けて、診断書や後遺障害診断書にその結果を具体的かつ適切に医師に作成してもらうことが重要です。脊柱に著しい変形や運動障害を残していると認められる場合は、1番重い6級5号が認定となります。
| 等級 | 基準 |
|---|---|
| 6級5号 | 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの |
| 8級相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |
| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
④荷重機能障害
腰椎圧迫骨折による荷重機能障害(かじゅうきのうしょうがい)とは、脊柱を支える機能が失われて、プラスチックや金属で作られた補装具である「硬性補装具が必要になる」ことを指します。 荷重機能障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、6級相当と8級相当です。 脊柱を支える筋肉が麻痺していたり、腰部周辺の軟部組織に器質的変化が認められることで、腰椎圧迫骨折による荷重機能障害を立証することができます。頚部と腰部の両方の保持が難しく、常に硬性補装具が必要な場合には6級相当が、頚部または腰部のいずれかの保持が難しく、常に硬性補装具が必要な場合には、8級相当が認定となります。
| 等級 | 基準 |
|---|---|
| 6級相当 | 頚部および腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの |
| 8級相当 | 頚部および腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの |
交通事故による腰椎圧迫骨折で争点になりやすいポイントと対策
示談交渉において、加害者側の任意保険会社は基本的に示談金の支払い額を抑えるために、様々な主張をしてきます。主に、次のような主張をしてくることが多いでしょう。
- ① 交通事故との因果関係について
- ② 後遺障害逸失利益の喪失率について
- ③ 素因減額の主張
では、それぞれの主張について、次項にて詳しく解説していきます。
交通事故との因果関係
そもそも、「腰椎圧迫骨折が事故によるものなのか」という“怪我と事故との因果関係”について、加害者側の任意保険会社から疑問があるとの主張を受けることがあります。 腰椎圧迫骨折は、事故による衝撃だけでなく、しりもちや軽い転倒でも起こり得る怪我です。そのため、事故前の日常生活で既に圧迫骨折が生じていて、事故後の転倒で追い打ちをかけるように悪化しただけであるという理由で、「100%事故によるものではない」と主張されることもあります。また、事故から病院を受診するまでに時間が経っている場合も、事故との因果関係がないと主張されやすいです。 因果関係を争わないためには、事故直後にMRI検査を受けて、事故による怪我だと証明できる証拠を残すことが重要です。
後遺障害逸失利益の喪失率
後遺障害逸失利益の喪失率とは、「労働能力喪失率」を指し、“後遺障害が原因で労働に支障が生じる割合”のことをいいます。そのため、後遺障害が重いほど労働に支障が生じると考えらえることから、労働能力喪失率は後遺障害が重ければ重いほど高くなります。 腰椎圧迫骨折の後遺障害のひとつである変形障害などは、骨が多少変形しても労働能力が失われるわけではないと、厳しく判断されることがあります。労働能力喪失率を争わないためには、後遺障害があることで「どのような業務がどれくらいできなくなったのか」など、業務への支障について細かく記録しておくと有効な証拠となり得るでしょう。
素因減額の主張
素因減額とは、“被害者が事故前から有していた素因(要素)が影響して損害が発生・拡大した場合に、その素因が影響した部分の賠償金を減額する”ということです。 たとえば、被害者が事故前から椎間板ヘルニアを患っていた場合などは、「事故前から既に症状があったのだから賠償金からその分を差し引くべきだ」という主張がなされやすいです。また、被害者が高齢者や骨粗鬆症の患者であった場合にも、素因減額を主張される可能性があります。 素因減額を主張されないためには、MRI検査や事故状況を証明する資料などを収集して、加害者側の任意保険会社と交渉しなければなりません。交渉は容易ではないため、法律のプロである弁護士にご相談されることをおすすめします。
腰椎圧迫骨折の慰謝料を適正額で受け取るためには?
腰椎圧迫骨折で入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などを適正額で受け取るためには、事故後から症状固定と診断されるまで“適切な頻度で治療を続けること”が大切です。 腰椎圧迫骨折で必要な検査はすべて受けるようにし、医師との診察では自覚症状を細かく伝え、医師に正確な診断書を書いてもらうことが重要となります。そのため、日常生活はもちろん、仕事上での支障についても具体的に医師へ伝えるようにしましょう。そうすることで、医師に作成してもらう診断書や後遺障害診断書の内容が充実したものとなり、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性を高めます。
腰椎圧迫骨折の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
腰椎圧迫骨折における慰謝料の請求を弁護士に依頼することで、次のようなメリットを得ることができます。
- 治療開始後から通院方法についてアドバイスを受けられる
- 加害者側の任意保険会社との交渉を一任できる
- 後遺障害等級認定の申請や異議申立ての手続きを代わりに行ってもらえる
- 弁護士基準を用いた慰謝料の請求ができる
- 訴訟に発展した場合にも、サポートしてもらえる など
腰椎圧迫骨折のような重症といえる事案では、入通院治療が必要となったり、治療期間が長くなったり、また、後遺症が残る可能性もあります。被った損害に見合う賠償金を受け取るためには、交渉のプロである弁護士に依頼することが有効な手段のひとつといえます。
腰椎圧迫骨折で後遺障害等級8級相当に認定され、約2300万円の賠償金を獲得できた事例
ご依頼者様は、相手方車両との衝突を避けようとハンドルを切ったものの、民家の堀に衝突してしまい、腰椎圧迫骨折を受傷しました。その後治療を続けましたが、残念ながら後遺症が残ってしまったため、弁護士にて後遺障害診断書の確認を行い、後遺障害等級認定の申請手続きを行いました。 後遺障害診断書の確認の際に、各所に記載漏れや不備が見受けられたことから、病院に対して診断書の追記や訂正依頼をしたうえで手続きを行いました。その結果、脊柱に中程度の変形があると認められ、8級相当の後遺障害等級が認定されました。 その後の賠償交渉では、逸失利益が争点となったものの、弁護士による粘り強い交渉の結果こちらの主張が認められ、約2300万円にて示談することができました。
交通事故による腰椎圧迫骨折に関するQ&A
腰椎圧迫骨折で後遺障害等級に認定されなかったらどうすればよいですか?
後遺障害等級認定を受けられなかった場合は、結果に対して再審査を求める「異議申立て」の手続きを行うことができます。 しかし、一度出た結果を覆すだけの新しい証拠が必要となるため、被害者の自覚症状を医学的に証明するに足りる効果的な資料を収集して、それを基に異議申立書という意見書のようなものを資料とあわせて提出しなければなりません。 この点、効果的な資料の収集には、専門的知識を要するため、異議申立ての手続きを行う際は、交通事故だけでなく医学的知識も有する弁護士のサポートを受けることが望ましいでしょう。
合わせて読みたい関連記事
腰椎圧迫骨折で複数の後遺障害が残った場合、慰謝料はどうなりますか?
異なる系列で複数の後遺障害等級認定を受けた場合には、1番重い後遺障害等級が繰り上げられ、「併合」として処理されます。 たとえば、13級以上の後遺障害等級が2つ認定された場合は、そのうち重い後遺障害等級の方を1つ繰り上げるという処理がなされます。そして、繰り上げられた等級に応じて後遺障害慰謝料の請求を行うことができます。 ただし、脊柱に変形障害と運動障害の後遺障害が残った場合には、どちらも同一系列であるとみなされるため、併合の処理は行われません。 いずれにしても、どのような形で併合の処理がなされたのかは、後遺障害等級認定通知書に記載されるため、そこで詳しく確認を行うことができます。
合わせて読みたい関連記事
腰椎圧迫骨折の後遺障害認定や慰謝料について、交通事故に強い弁護士がサポートいたします。
腰椎圧迫骨折により後遺症が残る場合、適正な後遺障害等級を得られれば、適正な後遺障害慰謝料を受け取ることができます。 適正な後遺障害等級が認定されるためには、腰椎圧迫骨折が存在すること、その骨折を原因とした症状が生じていることを医学的知見に基づいて立証しなければなりません。腰椎圧迫骨折という大変な怪我をして、その治療をしながらこうした作業をすることは非常に難しく、精神的にも大きな負担がかかることでしょう。 弁護士は、代理人として後遺障害等級認定申請や保険会社との交渉ができます。事故に遭われて間もない頃から賠償額が決まる最後まで、いわば被害者の方のパートナーとしてお手伝いができます。 弁護士法人ALGには、交通事故事案の経験が豊富な弁護士に加え、医療に強い弁護士も集まっております。腰椎圧迫骨折でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0078-6009-3003
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ


交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。