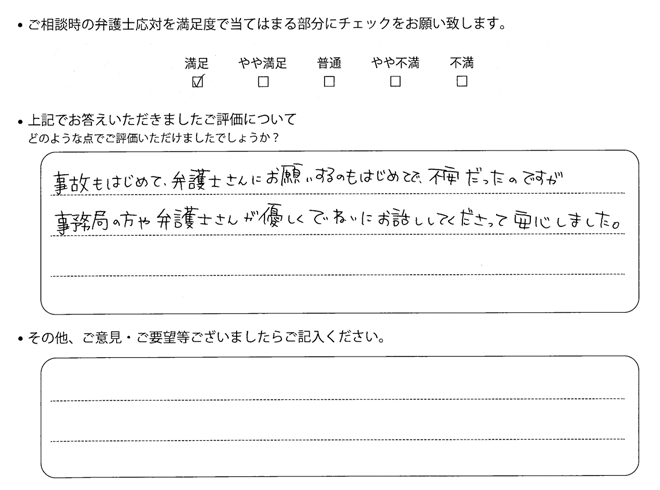主婦(主夫)の逸失利益は認められる?計算のポイントと計算例

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
主婦(主夫)の方が交通事故に遭ったとき、逸失利益が請求できるのか、不安に思われる方も多いでしょう。 逸失利益とは、交通事故に遭わなければ将来得られたはずの収入や利益のことです。 自分以外の誰かのための家事労働には経済的な価値があることが認められているので、主婦(主夫)であっても、交通事故により被害者が亡くなってしまった場合や、後遺障害が残ってしまった場合には逸失利益を請求することができます。 ただし、専業主婦(主夫)・兼業主婦(主夫)・高齢主婦(主夫)によって計算方法が異なるため、注意が必要です。 そこで今回は、【主婦(主夫)の逸失利益】について、計算のポイントを具体例や実例を交えつつ解説していきたいと思います。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-790-073
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
主婦(主夫)の逸失利益は認められる?
交通事故に遭ったのが主婦(主夫)であっても、逸失利益は認められます。 逸失利益は事故前の被害者の収入をベースに算出するため、現実的な収入を得ていない場合、主婦の逸失利益は認められないと思われがちです。 ですが、自分以外の誰かのために行う家事は、主婦にとっての仕事であり、外注すれば対価が発生することから、経済的な価値のあることが認められています。 そのため、交通事故によって家事労働を行う能力が損なわれたときは、「事故による減収があった」として、逸失利益を請求することができるのです。 交通事故の逸失利益には、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類があります。
| 後遺障害逸失利益 |
|
|---|---|
| 死亡逸失利益 |
|
主婦の逸失利益の基本計算式
まずは、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の基本的な計算式をおさえましょう。
後遺障害逸失利益
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
死亡逸失利益
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数(症状固定時から67歳までの期間)に対応したライプニッツ係数
基礎収入とは
基礎収入とは、被害者が交通事故前に現実に得ていた収入のことです。 専業主婦の場合は事故前に現実に得ていた収入がないので、厚生労働省の労働者賃金に関する統計データ「賃金センサス」に基づく「女性労働者の全年齢平均賃金」を基礎収入とします。
労働能力喪失率とは
労働能力喪失率とは、交通事故により後遺障害が残ったことで、労働能力がどの程度低下したのかを数値(パーセンテージ)で表したものです。 認定された後遺障害の等級に応じて次のとおり設定されていて、「後遺障害が何級に認定されるか」は逸失利益の算定において重要なポイントになります。
| 等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 第1級~第3級 | 100% |
| 第4級 | 92% |
| 第5級 | 79% |
| 第6級 | 67% |
| 第7級 | 56% |
| 第8級 | 45% |
| 第9級 | 35% |
| 第10級 | 27% |
| 第11級 | 20% |
| 第12級 | 14% |
| 第13級 | 9% |
| 第14級 | 5% |
なお、上記の労働能力喪失率はあくまで目安であり、後遺障害の部位や程度、年齢、仕事の内容によって喪失率は増減することがあります。 以下のページでは、後遺障害等級認定の要件や後遺障害等級が正しく認定されるためのポイントについて詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。
合わせて読みたい関連記事
労働能力喪失期間とは
労働能力喪失期間とは、交通事故により後遺障害が残ったことで労働能力が失われた期間のことです。基本的には、症状固定と診断された日から、就労可能年数である67歳までの期間を労働能力喪失期間とします。 労働能力喪失期間は、後遺障害の部位や程度、年齢、仕事の内容、健康状態などのさまざまな観点から調整されるケースがあります。 例えば、むちうちによる後遺症で14級の後遺障害等級が認定された場合、事故当時の年齢に関係なく、労働能力喪失期間は5年程度に制限されることが多いです。 以下のページでは、逸失利益をはじめとする交通事故の損害賠償金に大きく影響する「症状固定」について詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。
合わせて読みたい関連記事
ライプニッツ係数とは
ライプニッツ係数とは、将来得られるはずのお金を“今”まとめて受け取ることで発生する利息を控除するための係数です。ライプニッツ係数を使っていわゆる中間利息控除を行います。 将来受け取るお金を“今”受け取ることで、銀行に預けておくと利子がつきますし、運用すれば増やすこともできます。そのため、運用益を差引かないと、被害者が取得するべき以上の価値を被害者が受け取ってしまうことになるため、利息を控除することで調整するのです。
生活費控除について
生活費控除とは、事故での死亡後、被害者の生活費がかからなくなるため、逸失利益からその分を差し引き、調整することをいいます。 下表のように被害者の家庭内の役割、属性によって控除率が変わり、主婦(主夫)の場合には30%とされるケースが一般的です。
| 一家の支柱の場合かつ被扶養者1人の場合 | 40% |
|---|---|
| 一家の支柱の場合かつ被扶養者2人以上の場合 | 30% |
| 女性(主婦、独身、幼児等を含む)の場合 | 30% |
| 男性(独身、幼児等を含む)の場合 | 50% |
【ケース別】主婦の逸失利益を計算するポイント
専業主婦と兼業主婦とでは計算方法が違います。 また、年齢によっても変わることがあり、特に高齢の主婦(主夫)は特別な計算をすることがあるので注意が必要です。
専業主婦の場合
現実に収入を得ていない専業主婦の逸失利益は、賃金センサスに基づく「女性労働者の全年齢平均賃金」を基礎収入として計算します。
賃金センサスとは?
賃金センサスとは、厚生労働省が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の結果をもとに、労働者の平均賃金をまとめた資料のことです。
性別・年齢・職業・学歴などのさまざまな条件からみた平均賃金額を確認することができます。
なお、家事労働の重さは性別によって変わるものではないと考えられているので、公平の観点から、交通事故に遭ったのが男性の家事従事者である「専業主夫」の場合も、「女性」労働者の全年齢平均賃金を基礎収入として用います。
兼業主婦の場合
仕事と家事を両立している兼業主婦の場合も、逸失利益の計算式自体は専業主婦と同じです。 兼業主婦の逸失利益を計算するにあたっては、「実際の収入」と「女性労働者の全年齢平均賃金」を比較して、どちらか高額な方を基礎収入として用います。 「仕事と家事労働、どちらにも支障が出ているのだから両方の基礎収入を合算して請求したい」 このように思われる方もいらっしゃるかもしれません。 一般的に兼業主婦と専業主婦とでは、家事労働の密度に差があると考えられています。 そのため、「労働者の逸失利益」と「主婦の逸失利益」を二重取りすることは不合理だとして、どちらかでしか請求することができませんので注意しましょう。
高齢主婦の場合
高齢主婦であっても、逸失利益の計算式自体は基本的に専業主婦と同じです。 ただし、被害者の年齢や健康状態によっては、基礎収入や労働能力喪失期間に調整が必要になることがあります。
<基礎収入>
高齢主婦の場合、「通常の主婦と同等の家事労働はできない」として、全年齢平均賃金から何割か減額される、あるいは全年齢ではなく年齢別の平均賃金が用いられる可能性があります。
<労働能力喪失期間>
労働能力喪失期間を67歳までと区切っていることから、67歳を超えている場合や、67歳に近い年齢の場合には、簡易生命表の「平均余命の2分の1の期間」もしくは「67歳までの期間」を比較して、いずれか長い方が労働能力喪失期間として用いられます。
平均余命とは?
平均余命とは、ある年齢の人があと何年生きることができるのかを表した期待値のことです。
令和5年の簡易生命表によると、67歳男性の平均余命は17.94年、67歳女性の平均余命は22.59年でした。
なお、一人暮らしで無職の高齢者の場合、家族のために家事労働に従事しているとはいえないため、基本的に逸失利益を請求することはできません。
【計算例】後遺障害14級が認定された際の主婦の逸失利益
専業主婦の場合
36歳の専業主婦が、交通事故でむちうちを受傷し、後遺障害等級14級が認定された場合の後遺障害逸失利益を計算していきます。
- 事故前の現実の収入:なし
- 賃金センサス:399万6500円(令和5年女性労働者の全年齢平均賃金)
- 基礎収入:399万6500円(令和5年女性労働者の全年齢平均賃金)
- 労働能力喪失率:5%
- 労働能力喪失期間:5年
- 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数:4.580
これを計算式にあてはめると、次のようになります。
399万6500円×5%×4.580=91万5198円
このケースで専業主婦の方がもらえる後遺障害逸失利益は約91万円となります。
兼業主婦の場合
36歳の兼業主婦が、交通事故で鎖骨骨折を受傷して後遺障害等級14級・労働能力喪失期間10年が認められた場合の後遺障害逸失利益を計算します。
- 事故前の現実の収入:年収400万円
- 賃金センサス:399万6500円(令和5年女性労働者の全年齢平均賃金)
- 基礎収入:400万円(事故前の現実の年収)
- 労働能力喪失率:5%
- 労働能力喪失期間:10年
- 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数:8.530
これを計算式にあてはめると以下になります。
400万円×5%×8.530=170万6000円
このケースで兼業主婦の方がもらえる後遺障害逸失利益は約170万円です。
高齢主婦の場合
73歳の専業主婦が交通事故で手首骨折を受傷し、後遺障害等級14級・労働能力喪失期間7年が認められた場合の後遺障害逸失利益を計算します。
- 事故前の現実の収入:なし
- 賃金センサス:295万6900円(令和5年70代女性労働者の平均賃金)
- 基礎収入:295万6900円(令和5年70代女性労働者の平均賃金)
- 労働能力喪失率:5%
- 平均余命:17.40(令和5年簡易生命表)
- 労働能力喪失期間:7年
- 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数:6.230
これを計算式にあてはめると以下になります。
295万6900円×5%×6.230=92万1074円
このケースで高齢主婦の方がもらえる後遺障害逸失利益は約92万円です。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-790-073
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
主婦が逸失利益以外に請求できる賠償金
交通事故で賠償請求できるのは、逸失利益だけではありません。 ほかにも、以下のような請求費目がありますので、抜けがないようにチェックしておきましょう。
| 入通院慰謝料 |
|
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 |
|
| 治療費等 |
|
| 休業損害 |
|
以下のページでは、請求方法も併せて詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。
合わせて読みたい関連記事
主婦の逸失利益について弁護士法人ALGの解決事例
家事労働への支障等を主張したことにより、約650万円を増額させた事例
弁護士が家事労働への支障を主張したことにより、専業主婦の方の損害賠償金が約650万円増額した当法人の解決事例をご紹介します。
<事案の概要>
ご依頼者様は専業主婦で、交通事故で右鎖骨遠位端骨折を負い、事前認定にて後遺障害等級12級13号が認定されました。 相手方からは賠償金約150万円が提示されましたが、賠償案に納得がいかなかったため、当法人にご相談・ご依頼いただきました。
<弁護士の活動>
相手方提示の後遺障害逸失利益は労働能力喪失期間がわずか5年で計算されていました。 そこで弁護士は、長期間家事労働に支障が生じていたことや、後遺障害による労働能力の低下が大きいこと、後遺障害が今後も残存していく可能性が高いことを主張しました。
<結果>
相手方と交渉を続けた結果、労働能力喪失期間14年が認められ、最終的に約800万円の賠償金を支払ってもらう内容で示談が成立しました。
主夫としての基礎収入が認められ、約720万円の賠償金を得た事例
弁護士が示談交渉と後遺障害等級認定のサポートをすることで、主夫としての逸失利益が認められて約720万円の損害賠償金を獲得できた当法人の解決事例をご紹介します。
<事案の概要>
ご依頼者様は追突事故により、TFCC(三角線維軟骨複合体)損傷等の傷害を負われました。 相手方保険会社より一括対応の打ち切りを打診されたタイミングで、当法人に示談交渉等をご依頼いただきました。
<弁護士の活動>
弁護士のサポートにより、後遺障害等級12級が認定されました。 また、逸失利益についてはご依頼者様がお子様と二人暮らしであることから、赤字申告であった事故前年度の実収入ではなく、「兼業主夫」として「賃金センサスに基づく女性労働者の全年齢平均賃金」と同程度の基礎収入が認められる旨の主張を行いました。
<結果>
結果、弁護士の主張が全面的に通り、逸失利益のほか、治療期間中の休業損害も認められ、約720万円の賠償金を獲得することができました。
主婦でも逸失利益が認められる可能性があります。一度弁護士にご相談ください。
主婦(主夫)の逸失利益は計算が複雑です。 そのため、相手方保険会社から提示された逸失利益が適正な金額であるかどうか、ご自身で判断できないことも多いでしょう。 弁護士であれば、交通事故の被害に遭われた主婦(主夫)の方、それぞれの事情や事故被害の状況に応じた適切な基礎収入や労働能力喪失期間を用いて、逸失利益を計算することができます。 また、相手方との示談交渉を任せることもできるので、ご自身の負担を減らしつつ、適切な損害賠償金を獲得できる可能性が高まります。 相手方から主婦(主夫)は逸失利益が請求できないと言われたり、提示された逸失利益に納得できなかったりした場合は、交通事故の実務経験が豊富な弁護士が多く在籍している、私たち弁護士法人ALGへお気軽にご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-790-073
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ


交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。