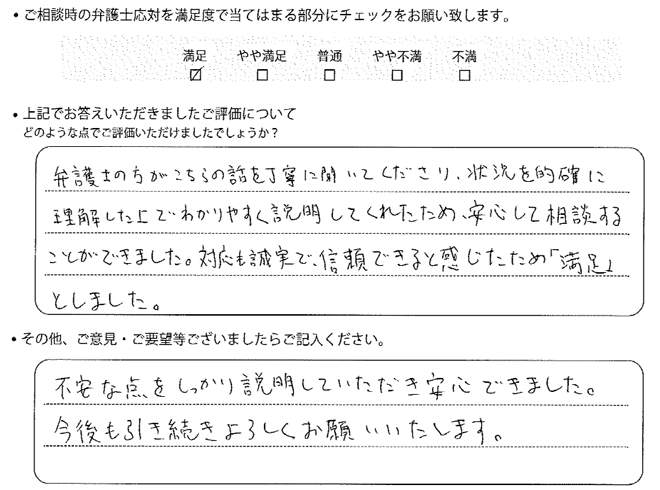交通事故の骨盤骨折で後遺障害は認定される?等級や慰謝料などを解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
骨盤骨折で後遺症が残ってしまった場合に生じる症状は多岐にわたります。 例えば、神経症状(歩行困難等)や、運動障害、変形障害、下肢の短縮障害、排尿障害です。また、骨盤骨折の他に合併損傷として他部の骨折をする場合も多く、痒痛や知覚障害を残す事例もあります。女性の場合は出産に支障が出てしまうこともあります。 骨盤骨折の後遺症は、このように多岐にわたるため、交通事故による骨盤骨折の症状に苦しまれている方は、早期に適切な治療を受けてその苦しみに見合った慰謝料を獲得することが大切です。 そこで本記事では、骨盤骨折における適切な後遺障害等級認定や慰謝料の相場について詳しく解説していきます。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-809-908
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
交通事故による骨盤骨折とは
骨盤骨折とは、“腰部や臀部(でんぶ)といった骨盤周辺の部位を強打することで起こる骨折”です。 骨盤は、運動や歩行はもちろん、上半身を支える、足からの衝撃を吸収する、一部の臓器および生殖器を保護するなど多岐にわたって非常に重要な役割を果たしています。複数の骨で構成される骨盤は、どの部位をどの程度損傷したかによって症状が変わるため、まずは整形外科でレントゲンやCT、MRIなどの画像検査を受けることが必要です。さらに女性であれば、尾骨の骨折により産道の狭窄なども起こり得るため、産婦人科も受診した方がよいでしょう。 また、交通事故で骨盤を骨折した場合に後遺症が残ることもあります。 骨盤骨折による代表的な症状は骨折部位への強い痛みですが、そのほかにも様々な症状が生じるおそれがあります。 例えば、歩行困難、排尿障害、痒痛、視覚障害等です。これらの後遺症はその程度に応じて1から14級に分類され、後遺症の賠償金を計算する基準となります。
骨盤骨折で認定される可能性がある後遺障害等級と基準
交通事故による骨盤骨折で後遺症が残った場合には、“後遺障害等級認定”を受ける必要があります。 後遺障害等級認定は、残存した後遺症の症状に応じて1~14級の等級に分類され、認定される等級によって賠償金額(慰謝料)の目安が決まります。 骨盤骨折として認定される可能性のある後遺障害の症状には、神経症状、変形障害、運動障害(可動域制限)などが挙げられますが、症状が生じているだけでは後遺障害等級認定を得ることはできません。 そこで次項では、認定される可能性のある症状と認定されるための要件について解説していきます。
合わせて読みたい関連記事
神経症状
骨盤骨折による痛みや痺れの症状は、“神経症状”の一種として後遺障害等級認定される可能性があります。骨盤骨折によって骨だけでなく神経の圧迫や損傷を伴うことから、骨折部位に痛みや痺れが生じます。 なお、骨盤骨折による神経症状で認められる可能性のある後遺障害等級は、下表のとおりです。
| 後遺障害等級 | 認定要件 |
|---|---|
| 12級13号 | 症状が神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見により、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と医学的に証明できること。 |
| 14級9号 | 症状を神経学的検査所見や画像所見などから証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、「局部に神経症状を残すもの」と医学的に推定できること。 |
後遺障害等級認定となれば、弁護士基準で12級224万円、14級75万円の保険金を受け取ることができます。
変形障害
骨盤骨折による“変形障害”とは、骨盤の骨折部位がうまく癒合できずに変形した状態となることです。 変形の程度が一定の基準(=裸体になったときに、外部から見て変形していることが明らかにわかる程度)を超えた場合には、「12級5号」に認定されます。
| 後遺障害等級 | 認定要件 |
|---|---|
| 12級5号 | 「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」と裸体になったときに目で見て明らかに分かる程度に判断できること。 |
運動障害(可動域制限)
骨盤骨折による“運動障害(可動域制限)”とは、股関節を動かせる範囲が制限されて歩行しづらいなど、可動域制限によって日常生活に支障を来す状態となることです。 運動障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、実際に股関節の可動域がどれほど制限されているかを調べ、一定の基準を超えた場合には制限の程度に応じて下表の後遺障害等級が認定となります。
| 後遺障害等級 | 認定要件 |
|---|---|
| 8級7号 | 股関節をまったく動かせないまたは骨折していない側の股関節と比べて10%以下しか動かせない状態で「1下肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの」と判断できること。 |
| 10級11号 | 股関節の可動域が骨折していない側の股関節と比べて2分の1以下の状態で「1下肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」と判断できること。 |
| 12級7号 | 股関節の可動域が骨折していない側の股関節と比べて4分の3以下の状態で「1下肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの」と判断できること。 |
正常分娩困難
骨盤骨折による“正常分娩困難”とは、変形障害等により女性の産道が狭窄してしまい正常分娩が困難となり、帝王切開での出産を余儀なくされる状態になることをいいます。 正常分娩困難で認定される可能性がある後遺障害等級は、正常分娩が困難と判断できる原因の程度によって下表の後遺障害等級が認定となります。なお、正常分娩困難は整形外科での画像検査の結果をもとに産婦人科で診断してもらう必要があるため、注意が必要です。
| 後遺障害等級 | 認定要件 |
|---|---|
| 9級17号 | 産婦人科で診察を受け、「生殖器に著しい障害を残すもの」と判断できること。 |
| 11級10号 | 産婦人科で診察を受け、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」と判断できること。 |
勃起障害
骨盤骨折による“勃起障害”とは、骨盤骨折で生じた血管や神経の障害が原因で十分に勃起することができなくなる状態をいいます。勃起障害が疑われる場合には、泌尿器科を受診し、勃起障害を立証するための検査を受ける必要があるでしょう。 男性に生じる勃起障害で認定される可能性がある後遺障害等級は、生殖器の障害の程度によって下表の後遺障害等級が認定となります。
| 後遺障害等級 | 認定要件 |
|---|---|
| 9級17号 | 診断結果や検査結果から、「性器に著しい障害を残すもの」と判断できること。 |
| 11級10号 | 診断結果や検査結果から、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」と判断できること。 |
下肢の短縮障害
骨盤骨折による“下肢の短縮障害”とは、骨盤骨折で骨盤が歪み、足の長さが変わってしまう状態になることをいいます。 下肢の短縮障害で認定される可能性がある後遺障害等級は、短縮してしまった足と正常な足の長さを比較して一定基準を超える差が生じた場合に、長さの差に応じて下表の後遺障害等級が認定となります。
| 後遺障害等級 | 認定要件 |
|---|---|
| 8級5号 | 左右の上前腸骨棘(腰骨の突出した部分)から下腿内果(内くるぶし)までの長さをそれぞれ測り、左右差が5㎝以上で「1下肢を5センチメートル以上短縮したもの」と判断できること。 |
| 10級8号 | 左右の上前腸骨棘(腰骨の突出した部分)から下腿内果(内くるぶし)までの長さをそれぞれ測り、左右差が3㎝以上で「1下肢を3センチメートル以上短縮したもの」と判断できること。 |
| 13級8号 | 左右の上前腸骨棘(腰骨の突出した部分)から下腿内果(内くるぶし)までの長さをそれぞれ測り、左右差が1㎝以上で「1下肢を1センチメートル以上短縮したもの」と判断できること。 |
骨盤骨折で適切な後遺障害等級認定を受けるためには
骨盤骨折による後遺症が残っても、残念ながら後遺障害等級認定を受けられないこともあります。 後遺障害等級認定を受けるためには、後遺症として残った症状が事故によるものだと証明しなければなりません。証明するに値する資料が乏しいと判断されればすぐに非該当となるため、適切な後遺障害等級認定を受けることは決して容易ではないのです。 では、どうすれば適切な後遺障害等級認定を受けることができるのでしょうか? 次項にて、そのポイントについて詳しく解説していきます。
医師に症状を正確に伝える
適切な後遺障害等級認定を受けるためには、初診から医師に自覚症状を正確に伝えることが重要です。 「いつから、どこが、どのような状態か」などの自覚症状を医師に正確に伝えることで、症状が生じている原因を追究するために必要な検査を行ったり、診断書にその事実を記載したりするため、医学的証拠となる診断書などの精度が上がります。 その結果、事故と症状との因果関係が証明しやすくなるため、どんなに些細な症状であっても、遠慮せずに医師へしっかりと伝えることが大切です。
適切な検査や治療を受ける
症状に応じて各種検査を受け、医師の指示に従い適切な頻度で治療することも適切な後遺障害等級認定を受けるうえで重要となります。 後遺障害等級認定の審査では、他覚的所見の有無が注目されます。 そのため、等級認定に必要な検査がされていなかったり、医師の指示に背いて通院していない(少ない)場合には、適切な後遺障害等級認定を受けられない可能性が高まります。 また、通院頻度が少なければ、「治療する必要がない=痛みなどが生じていない」と判断されてしまうため、医師の指示に従って適切な通院頻度で治療を継続することが大切です。
正確な診断書を書いてもらう
後遺障害等級認定は、医師が作成する「後遺障害診断書」で判断されると言っても過言ではありません。 なぜなら、後遺障害等級認定は書面審査であるため、後遺障害診断書に記載がないことについては深く追及しないからです。 医師は後遺障害等級認定の専門家ではないため、認定のための診断書としては抜けがある場合があります。そのため、他覚的所見や自覚症状などについてはっきりと記載されているか確認し、曖昧な表現があれば書き直してもらうことが大切です。 この点、交通事故を得意分野とする経験豊富な弁護士であれば、診断書の漏れなどをしっかりチェックすることができるため、安心して任せることができるでしょう。 以下のページでは、後遺障害診断書の書き方について詳しく解説しております。 ぜひご参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
弁護士に相談・依頼する
ひとりで適切な後遺障害等級認定を受けるために必要な知識を得るには、どうしても限界があります。 そのため、交通事故を専門とし、特に後遺障害に詳しい弁護士へ相談・依頼することも重要です。 交通事故事案を多く取り扱い、豊富な知識と経験がある弁護士であれば、適切な後遺障害等級認定を受けるために必要な検査のアドバイスや診断書のチェックを行ってもらえます。診断書に漏れがあれば、どのように修正すればよいのかなどのアドバイスを受けられるため、より豊富な知識を得ることができます。 また、認定結果に納得できない場合には、結果に対して異議申立てを行うこともできますが、異議申立てのサポートもしてもらえるため、より安心して手続きを行うことができるでしょう。
骨盤骨折で後遺障害が残った場合の慰謝料相場
骨盤骨折で後遺障害等級認定を受けた場合、認定された等級に応じて“後遺障害慰謝料”を請求することができます。
後遺障害慰謝料とは?
交通事故による怪我で後遺症が残ってしまったことで被った精神的苦痛に対する補償金をいいます。
交通事故における慰謝料の算定には、以下の3つの基準があります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判基準)
この3つの基準の中でもっとも高い基準となるのが、“弁護士基準”です。 弁護士基準は過去の裁判例をもとに設定された基準であるため、被害者に生じた損害を補償するのに1番適した基準といえます。 骨盤骨折で認定される可能性がある後遺障害等級ごとの自賠責基準・弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場を表でみてみましょう。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
このように、認定される等級の数字が小さいほど後遺障害慰謝料が高額となり、算定基準によって後遺障害慰謝料の金額が大きく異なります。 上表をみると、自賠責基準よりも弁護士基準の方が2~3倍ほど高額となることがわかります。
骨盤骨折で後遺障害が認められた裁判例
【大阪地方裁判所 平成17年1月31日判決】
<事案の概要>
信号機のある交差点で、原告が運転する自転車と後方から走行してきた被告車両が接触した交通事故において、原告が転倒した際に骨盤骨折等を受傷し人工肛門を装着しなければならなくなったため、被告側に対して損害賠償請求した事案です。
<裁判所の判断>
自賠法に基づく後遺障害等級認定では、骨盤骨折後の右腸骨から寛骨の変形障害については12級5号、肛門周囲裂創に伴う人工肛門の設置については9級11号が認定となり、「併合第8級」であることが認められました。 裁判所は、上記の症状の他に頭痛、右手痺れ感、右下腹部痛等の痛みについても14級12号に該当すると認めましたが、骨盤骨折後の症状については自賠責と同様の認定がされ、併合第8級相当であるとの判断は変わりませんでした。 しかしながら、骨盤の変形障害により産道が狭窄し正常分娩が困難な状況であること、女性でありながら生涯にわたり人工肛門を装着しなければならないこと、腹部や大腿部に複数の醜状痕を残していること等を考慮し、後遺障害慰謝料について1200万円(370万円の増額)を認めました。その結果、本事案では総額として、後遺障害慰謝料を含む損害賠償金5202万9651円の請求が認められました。
交通事故による骨盤骨折の後遺障害認定は弁護士にご相談ください
骨盤骨折は、折れた部位や程度によってより重篤な症状につながるおそれがあります。後遺症が残る重い症状を負ったときには、後遺障害等級認定の申請を行い、症状に見合った賠償をしっかりと受けるべきです。しかし、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、多くの医学的証明が必要となります。 また、専門科である整形外科だけでなく、内科や婦人科などの他科を横断することも多く、適切な診断を受けるために様々な診療科の医師に診てもらうという必要性もあります。 そのため、ご自身で抱え込まずに弁護士へ相談し、交渉や示談までの手続きについて助言を得ることをおすすめします。特に医療分野に精通し、後遺障害等級の申請も経験豊富な弁護士であれば、より安心して任せることができるはずです。骨盤骨折でお悩みの方は、お気軽に弁護士へご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-809-908
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ


交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。