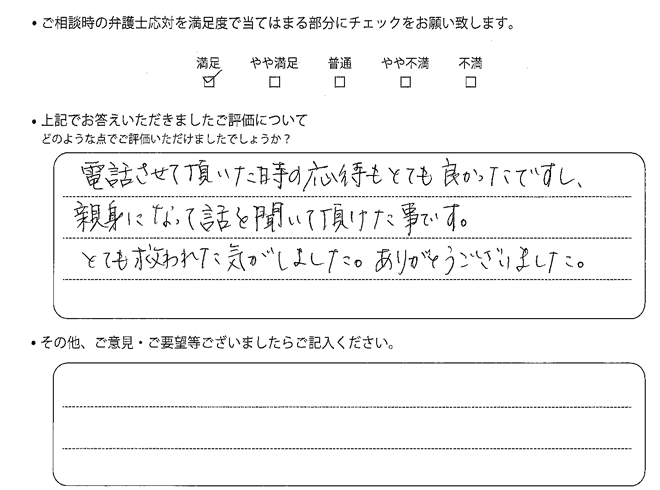交通事故による可動域制限の後遺障害|等級認定の要件や慰謝料などを解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故により骨折や靭帯損傷になると、肩、膝、足の関節が今まで通り曲がらなくなることがあります。このような症状を“可動域制限”といいます。 一定の可動域制限が身体に残り、後遺障害等級認定を受けると「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を請求することができます。 この記事では「可動域制限」に着目し、可動域制限の症状や、後遺障害等級の認定について解説していきます。可動域制限で請求できる後遺障害慰謝料の解説も交えていきますので、本記事にてしっかりと理解を深めていきましょう。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-630-807
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
交通事故による可動域制限とは
交通事故による可動域制限とは、“交通事故が原因で肩や肘などの関節を動かせる範囲が狭くなってしまうこと”をいいます。 可動域制限が残ると、物をうまく掴めなかったり、歩行困難が生じたりします。また、股関節の可動域が制限されるとバランスが取れず転倒しやすくなるなど、日常生活に多大な影響を及ぼします。 交通事故では、骨折、脱臼、神経が麻痺してしまうような重大な怪我を負った場合に可動域制限の症状が現れることが多いです。そのほかにも、人工股関節の挿入手術を受けた際に可動域制限が現れることがあります。 治療を続けても可動域制限が残ってしまった場合には、「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。適切な後遺障害等級認定を受けるためには、事故との因果関係が認められ、可動域制限があることをレントゲンやMRI検査などで医学的に説明・証明できなければなりません。
可動域制限で後遺障害認定されるための要件
可動域制限で後遺障害等級が認定されるためには、①~③のいずれかに該当する必要があります。
- ①関節の「用を廃したもの」
- ②関節の「著しい機能障害」
- ③関節の「機能障害」
以下の表で詳しくみていきましょう。
| ①関節の「用を廃したもの」 |
・関節が完全に固まって動かない状態か、それに近い状態※ ・関節が完全弛緩性麻痺で動かないか、これに近い状態※ ・人工関節や人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度と比べて2分の1以下に制限された状態 ※可動域が健側の10%程度以下の状態 |
|---|---|
| ②関節の「著しい機能障害」 |
・可動域が健側と比べて2分の1以下に制限された状態 ・人工関節を挿入置換した関節のうち、可動域が健側と比べて2分の1以下に制限された状態以外のもの |
| ③関節の「機能障害」 | 関節の可動域が健側と比べて4分の3以下に制限された状態 |
健側とは
半身に麻痺や障害を負っている場合における障害がない側の身体を指します。
可動域制限で認定される可能性のある後遺障害等級
可動域制限で認定される可能性のある後遺障害等級には、1級・5級・6級・8級・10級・12級が挙げられます。 後遺障害等級認定の申請手続きは、一般的に医師から「症状固定」と診断されたときに行います。症状固定とは、医師から治療を続けても良くも悪くもならないと判断されることをいいます。 また、後遺障害等級は1級~14級に分類され、もっとも症状が重いものが1級となります。後遺障害は、さらに細かく部位や障害の性質に応じて35の系列に分類されており、可動域制限の程度は後遺障害の等級に大きく関わってきます。 では、後遺障害の程度と後遺障害等級の関係について、もう少し掘り下げてみていきましょう。
上肢(肩・肘・手首)の可動域制限と等級
上肢(じょうし)とは、肩から指先までのことです。そのため、上肢の3大関節や手指の関節に可動域制限が残った場合、後遺障害等級が認定される可能性があります。 この場合に考えられる後遺障害等級と内容は以下のとおりです。
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
| 5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
| 6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| 8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
下肢(股・膝・足首)の可動域制限と等級
下肢(かし)とは、股関節から足の指先までのことです。そのため、下肢の3大関節や足指の関節に可動域制限が残った場合、後遺障害等級に認定される可能性があります。 この場合に考えられる後遺障害等級と内容は以下のとおりです。
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
| 5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
| 6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| 8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
可動域制限で請求できる後遺障害慰謝料
後遺障害として認められると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の請求が可能となります。交通事故における慰謝料の計算では、次の3つの基準のうちいずれかを用いることが一般的です。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
このうち、任意保険基準の内容については、各保険会社が独自で決めていることから公表されていません。そのため、一般的には自賠責基準と弁護士基準を比較した表が用いられることが多いです。 なお、自賠責基準は、「基本的な対人賠償の確保を目的とした基準」であるため、弁護士基準よりも低い算定基準となっています。 たとえば、下表の後遺障害等級12級でみてみると、自賠責基準は後遺障害慰謝料が94万円に対して弁護士基準では290万円と金額に大きな差があります。適切な後遺障害慰謝料を受け取るためには、弁護士基準で計算することが大切です。
| 等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級(要介護) | 1150万円(1650万円) | 2800万円 |
| 5級 | 618万円 | 1400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1180万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
なお、以下のページでは、入力するだけで簡単に損害賠償金の目安を自動計算することができます。 ぜひご参考になさってください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-630-807
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
可動域制限で後遺障害等級認定を受ける3つのポイント
可動域制限で後遺障害等級認定を受けるためには、次の3つのポイントを押さえることが大切です。
- ①症状固定まで治療を受ける
- ②適切な検査方法で可動域制限を証明する
- ③後遺障害診断書の内容をよく確認する
では、それぞれのポイントについて、詳しく解説していきます。 3つのポイントを押さえて適切な後遺障害等級認定を受けましょう。
①症状固定まで治療を受ける
身体に残ってしまった可動域制限について、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、症状固定まで治療を続けることが重要です。 症状固定は、これ以上治療を続けても良くも悪くもならない状態であることを指し、医師によって判断されます。また、可動域制限の症状に関わらず、後遺障害等級認定を受けるためには、少なくとも6ヶ月以上は治療を定期的に受ける必要があります。なぜなら、治療期間が短い・通院頻度が少ない場合は、「しっかりと通院していれば症状が緩和していたかもしれない」と疑問視され、後遺障害として認められる可能性が低くなるからです。 そのため、「しっかりと通院して治療したが、それでも症状が残った(=後遺障害)」ということをアピールするために、医師から症状固定と判断されるまではきちんと治療を続けることが大切です。
②適切な検査方法で可動域制限を証明する
可動域制限で後遺障害等級認定を受けるためには、交通事故による怪我が原因で可動域制限が生じていることを医学的に証明する必要があります。ただ関節に可動域制限があると主張しても、後遺障害は認定されません。そのため、具体的には、画像検査や可動域検査で関節の可動域制限の原因を明らかにし、確かに可動域が制限されていることを示す必要があります。 可動域は、一般的にX線、CT、MRIなどで関節がどれだけ動くのかを調べます。可動域検査は、可動域制限が生じていない方の測定値と比較して異常があるのかを確認し、測定値は自分で関節を動かす「自動値」ではなく、医師が手で動かして測る「他動値」が用いられます。 身体に可動域制限が生じているのかを確かめる測定法について、詳しくは以下をご覧ください。 可動域制限が生じている部位によって様々な測定法があります。
③後遺障害診断書の内容をよく確認する
後遺障害等級認定の申請手続きに必須な「後遺障害診断書」の内容をよく確認することも非常に重要となります。 後遺障害診断書は、医師が症状固定と判断した後に医師によって作成することができる書面です。作成してくれるからといって医師に任せきりにせず、これまで伝えてきた自覚症状や検査の内容が間違っていないか自分でも内容をよく確認しましょう。 とはいえ、書かれている内容が難しく、正しいのか判断がつかない場合もあるはずです。そのような場合には、後遺障害等級認定に詳しい弁護士へご相談されることをおすすめします。
なお、以下のページでは、後遺障害等級認定を有利に受けるための基本について解説しています。 後遺障害診断書の書き方についても詳しく解説しておりますので、ぜひご参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
交通事故による可動域制限で後遺障害等級10級が認められ、賠償金約2500万円で示談できた事例
| 賠償金 | 未提示 ➡ 約2500万円 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 非該当 ➡ 10級10号 |
| 傷病名 | 肩関節機能障害 |
ご依頼者様は、バイクで走行中に相手方車両に衝突され、肩関節機能障害を負いました。その後、約1年間の入通院を続けましたが、肩関節に可動域制限が残ったため、弁護士にて後遺障害等級認定の申請手続きを行いました。しかし、外傷性変化が認められなかったことで結果は非該当でした。 そこで、以前撮影されたMRIについて画像鑑定を行い、肩関節における外傷所見を明確にしたうえで異議申立てを行いました。その結果、「肩関節部分に機能障害の原因となる外傷性変化が認められる」として10級10号の認定を得られました。 その後の示談交渉でも、後遺障害等級認定の結果に基づき粘り強く交渉を行い、最終的に自賠責保険金を含めた約2500万円にて示談することができました。
交通事故による可動域制限の後遺障害について、弁護士が親身にアドバイスさせていただきます。
交通事故に遭い可動域制限が残ってしまうと、日常生活に多大な影響を及ぼすため、後遺障害等級認定を受けることが適切な補償を受けるうえで重要です。 しかし、可動域制限の後遺障害等級認定の手続きを自分で行う場合、必要書類の作成や資料の収集で多くの時間と労力を要してしまいます。 そのため、可動域制限でお困りの方は、ぜひ交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。 治療中の段階から弁護士に相談することで、後遺障害等級認定を見据えた治療のアドバイス等を受けられるだけでなく、申請に必要な書類のほとんどは弁護士に集めてもらえるため、ご自身で煩雑な手続きを行う必要がなくなります。弁護士基準で慰謝料を請求することもでき、増額にも期待できるため、可動域制限の後遺障害等級認定でお悩みの方は、弁護士法人ALGにご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-630-807
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ


交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。