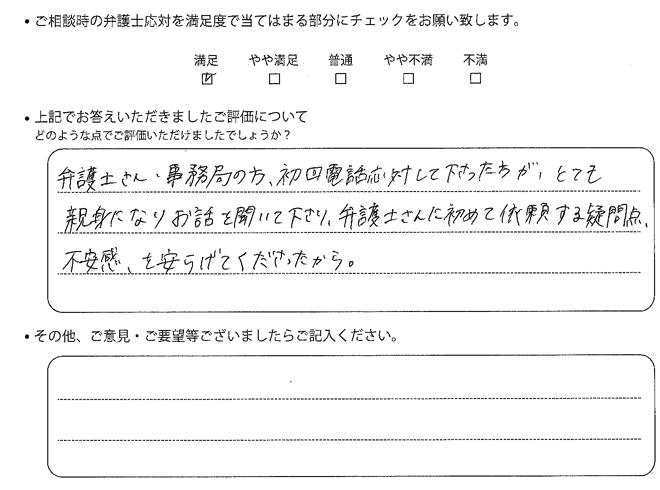死亡事故の慰謝料相場はいくら?遺族が適切な金額を受け取るためには

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
突然の交通事故で大切な命を失ったとき、被害者の無念さやご遺族の深い悲しみは言葉では言い尽くせません。 せめて残されたご遺族の心が少しでも慰められるように、【死亡事故の慰謝料】について適切な金額や請求方法を本記事で分かりやすく解説していきます。 交渉相手となる保険会社から提示される慰謝料額は必ずしも適切とは限りませんので、後悔のない解決を目指すためにも、ぜひ参考になさってください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
交通事故の死亡慰謝料とは?
交通事故の死亡慰謝料とは、事故によって被害者が亡くなったことによる多大な精神的苦痛に対する賠償金のことです。 命の価値は金銭で測れるものではありませんが、被害者の無念や遺族の悲しみに対する社会的な償いとして慰謝料が支払われます。 死亡慰謝料は「被害者本人の分」と、事故により大切な家族を奪われた「遺族の分」の2種類があります。
被害者本人の慰謝料
「亡くなっている被害者本人の慰謝料がもらえる」というのは不思議な感覚もあるでしょうが、事故で突然人生を奪われてしまった苦痛は計り知れません。このため、たとえ亡くなっているとしても、賠償を受けることが“被害者の権利”として認められています。 ただし、被害者は亡くなっているので、法律的には遺族である配偶者、子供、父母、兄弟姉妹などが”被害者の権利”を相続するかたちで受け継ぐことになります。 相続人が複数いる場合には、話し合いなどによる変更がない限り、法律で決まっている割合によって分割されます。
遺族の慰謝料
死亡事故では、被害者本人の慰謝料だけでなく、遺族が受け取れる慰謝料(近親者固有慰謝料)もあります。 家族を突然失った遺族は深い悲しみや精神的な苦痛を負うため、被害者本人の慰謝料とは別に、遺族自身の権利として賠償を受けられる仕組みです。 民法第711条では、慰謝料を請求できる遺族は「被害者の父母・配偶者・子供」とされていますが、実際には「祖父母・兄弟姉妹・孫・内縁の配偶者」なども、被害者との関係や生活状況によって認められる場合があります。
死亡事故の慰謝料の相場はいくら?
交通事故の死亡慰謝料の相場は、自賠責基準の場合で400万~1350万円程度、弁護士基準では2000万~2800万円程度です。 交通事故の慰謝料は、死亡慰謝料を含めておおよその金額を算定するための基準が3つ存在します。
| 自賠責基準 | 法令で定められているため確実性が高い一方、“最低限度の補償”に留まるため、基本的に最も低い算定金額となる。 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 保険会社ごとに独自に設けられている基準。 基本的に社外秘扱いで非公開のため詳細を知ることはできないが、営利企業の保険会社が算定していることから、自賠責基準と同等か少し上乗せした程度の算定金額となる。 |
| 弁護士基準 | 過去の裁判例の実績のもとに示された基準。 算定結果は3つの中で最も高額となるのが基本だが、実際の裁判に基づいた結果であることから最も正当な金額といえる。 ただし、使用できるのは基本的に弁護士に限られるのが実情。 |
一般的に、【自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準】の順で慰謝料が高額になることが多く、示談交渉の際に「どの算定基準を適用するか」が受け取れる金額を大きく左右します。 任意保険基準は非公開のため、以降では自賠責基準と弁護士基準について詳しくみていきましょう。 以下ページの「損害賠償額計算ツール」では、項目にしたがって入力していくだけで、死亡慰謝料を含む損害賠償額を簡単に計算することができます。 ぜひご活用ください。
合わせて読みたい関連記事
自賠責基準の場合
自賠責基準の死亡慰謝料は、「本人分」と「遺族分」が別枠で設けられているのが特徴です。 本人分の金額は400万円(※)と一律で決まっており、遺族分は請求する権利が被害者の父母・配偶者・子供とされていて、請求する者の人数によって金額が異なります。
| 死亡慰謝料 | |
|---|---|
| 被害者本人 | 400万円 |
| 請求者1人 | 550万円 |
| 請求者2人 | 650万円 |
| 請求者3人以上 | 750万円 |
| 被扶養者がいる場合 | 200万円 |
※令和2年4月1日に自賠責基準が改正されており、改定前の事故に関しては本人分が350万円と金額が異なる点にご注意ください。
<例>
【夫が死亡した場合で、妻と子供2人が扶養に入っていたケース】でいうと ・被害者本人分の慰謝料:400万円 ・遺族分の慰謝料:750万円(妻と子供2人)+200万円(被扶養者あり) ・死亡慰謝料の合計:1350万円(400万円+750万円+200万円) したがって、このケースについて自賠責基準で受け取れる死亡慰謝料は1350万円となります。
弁護士基準の場合
弁護士基準の死亡慰謝料は、「本人分」と「遺族分」を合わせた金額となっています。 さらに、「生前の被害者が家庭内でどのような立場・役割だったか」によって金額が異なるのが特徴です。
| 亡くなった人 | 死亡慰謝料 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2800万円 |
| 母親・配偶者 | 2500万円 |
| その他 | 2000万~2500万円 |
<例>
【夫が死亡した場合で、妻と子供2人が扶養に入っていたケース】でいうと、事故で亡くなった人は一家の支柱に当たるので2800万円となり、自賠責基準よりもはるかに高額な死亡慰謝料となるのがわかります。 ただし、弁護士基準は裁判を前提とした基準ですので、弁護士以外の方がこの基準をもとに主張しても聞き入れてもらえないのが実情です。 事故で亡くなったのが高齢者の場合、「仕事をして家計を支えていた」などの特段の事情がなければ、慰謝料は2000万~2500万円が目安となります。
死亡慰謝料が増額されるケース
交通事故の死亡慰謝料は、弁護士基準によって「受け取るべき金額の目安」を算出できますが、事故の悪質性や加害者の態度、被害者や遺族の具体的な事情を考慮して相場から増額されるケースもあります。
- 事故の悪質性
- 殺人ととらえられてもおかしくないような酷い事故態様
- 複数名が死亡するような事故態様
- 飲酒運転、無免許運転、薬物服用運転、スピード違反、信号無視、ひき逃げ、など
- 加害者の態度
- 加害者による謝罪がなかった
- 遺族に対して暴言を吐いた
- 証拠隠滅があった
- 被害者や遺族の特別な事情
- 被害者が子供で、両親や兄弟姉妹が受けた精神的苦痛が甚大であった
- 被害者が妊娠していて、胎児も一緒に亡くなってしまった
死亡慰謝料が減額されるケース
交通事故の死亡慰謝料は、被害者側に過失があって「過失相殺」されたり、被害者がもともと有していた素因による「素因減額」をされたりして、減額されるケースもあります。
・過失相殺
事故で亡くなってしまったとはいえ、被害者に注意義務違反や交通違反などがあった場合には被害者側にも過失がつき、これに応じて慰謝料が減額されることがあります。
・素因減額
持病や既往症など、被害者が有していた心因的素因や身体的素因が原因で事故による損害の発生や拡大に影響したと判断された場合に、これに応じて慰謝料が減額されることがあります。
死亡慰謝料を請求する流れ
死亡慰謝料は、加害者側と示談交渉をすることで請求できます。 示談交渉は、葬儀費用などの損害額が確定した後に始めるのが一般的で、遺族の心情に配慮し、四十九日法要が終わってから行うケースが多いです。 示談が成立すると、合意内容に基づいて慰謝料を含めた示談金が支払われます。 もっとも、死亡事故は賠償額が大きくなる傾向にあるため、交渉がまとまらないケースも少なくありません。 示談が不成立となった場合は、訴訟を提起し、最終的に裁判所に決定してもらいます。 遺族が落ち着かれたタイミングで示談交渉が行われるとはいえ、それでも辛い場面が出てくることもあるでしょう。 無理をせず、正当な賠償を求めるためにも、弁護士への相談をおすすめします。
死亡慰謝料の請求には時効がある?
死亡慰謝料を含む損害賠償の請求権には、時効がある点に注意が必要です。 時効は以下のいずれかとなります。
- 加害者がわかっている場合:死亡日の翌日から5年
事故時に加害者がわかっている場合には、死亡日の翌日から起算して5年が過ぎると時効成立となります。 - 加害者がわからない場合:加害者がわかった翌日から5年
ひき逃げなどで事故時(死亡時)に加害者がわからず、後日判明した場合には、加害者がわかった翌日を時効の起算日とします。 - 事故日の翌日から20年
ひき逃げなどで加害者がわからないままのケースがこれに該当します。
なお、時効の成立を延長させる手続きもあります。 差し迫っている方は、弁護士に相談するのもひとつの手です。
受け取った死亡慰謝料を分配する方法
遺族の慰謝料は、請求権を有する遺族(被害者の父母・配偶者・子供など)が受け取ります。 一方、被害者本人の慰謝料は、相続人が受け取り、相続人の間で分配されます。 分配方法について、亡くなった被害者本人の遺言書があればその内容に従って分配しますが、突然の事故で遺言書がない場合も多いでしょう。 遺言書がない場合は、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」で分配方法を決めるか、「法定相続分」に従って分割することになります。
| 相続人 | 相続の割合 |
|---|---|
| 配偶者と子供 | 配偶者1/2、子供1/2 ※子供が複数名いる場合は、子供1/2の分を人数で分け合うこととなります。 |
| 配偶者と親 | 配偶者2/3、親1/3 ※両親で分ける場合は、親1/3の分を分割することとなります。 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 ※兄弟姉妹が複数名いる場合は、兄弟姉妹1/4の分を人数で分け合うこととなります。 |
| 親と子供 | 子供のみ |
| 親と兄弟姉妹 | 親のみ |
| 配偶者のみ | 配偶者のみ |
| 子供のみ | 子供のみ ※複数名いる場合は、均等に分け合うこととなります。 |
| 親のみ | 親のみ ※両親で分ける場合は、1/2ずつ分け合うこととなります。 |
| 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹のみ ※複数名いる場合は、均等に分割することとなります。 |
被害者本人の慰謝料を分配する際、相続人の間で相続分についてもめるケースもあるため、あらかじめ弁護士に相談しておくことをおすすめします。
死亡事故の慰謝料に相続税などの税金はかかる?
交通事故の死亡慰謝料には、相続税をはじめとした税金はかかりません。 死亡慰謝料だけでなく、ほかの交通事故の損害賠償金も同様で、基本的には非課税です。 ただし、次に挙げるような金銭を受け取った場合は「利益とみなされるお金」として例外的に税金の課税対象となる可能性があります。
- 高額な見舞金を受け取った場合
損害賠償の範囲を超えて、加害者から見舞金といった名目で過剰に高額な金銭を受け取った場合は贈与税、被害者の勤務先から高額な見舞金を受け取った場合は所得税の対象となることがあります。 - 過失分の人身傷害保険金を受け取った場合
過失相殺による減額分を補填するために、被害者自身の人身傷害保険から保険金を受け取った場合、過失相殺相当分が所得税の対象となることがあります。 - 死亡保険を受け取った場合
搭乗者損害保険や自損事故保険から死亡保険金を受け取った場合、保険契約に基づく給付とみなされて所得税の対象となることがあります。
交通事故慰謝料の税金については、以下のページでより詳しく解説しています。 ぜひ参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
死亡事故で慰謝料以外に請求できる損害賠償金
死亡事故の場合に、死亡慰謝料とは別に請求できる損害賠償費目を整理しておきましょう。
- 死亡逸失利益
- 葬儀関係費用
事故後搬送され入院後に亡くなった場合などは、その分の損害についても請求することができます。
- 治療費(入院雑費、付添看護費用または休業損害、付添人・近親者の交通費)
- 入通院慰謝料
- 被害者の休業損害
- (裁判をした場合)弁護士費用
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、被害者が交通事故で亡くならなければ得られたはずの将来の収入のことです。 死亡逸失利益は、次の計算式で算出されます。
<死亡逸失利益の計算方法>
基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
亡くなった被害者が収入のない主婦(主夫)や子供であっても、賃金センサスの平均賃金によって死亡逸失利益を算出できます。 特に、亡くなった被害者の収入が多かった場合や、亡くなった被害者の年齢が若い場合には、それだけ失われる将来の収入が大きくなります。 交通事故の損害賠償金のなかでも、死亡逸失利益は金額が大きくなる傾向にあるため、正当に受け取れるよう交通事故に詳しい弁護士へ相談するといいでしょう。 交通事故の逸失利益について、詳しくは以下のページを参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
葬儀関係費用
被害者の葬儀にかかわる費用も、死亡慰謝料とは別に請求することができます。 例えば、葬儀、法要、火葬、墓石、仏壇・仏具といった費用が対象となります。 これらについて、基本的に実費を請求できるのですが、算定基準ごとに上限がありますのでご注意ください。
自賠責基準:一律100万円
弁護士基準:上限150万円
なお、被害者が会社役員のため葬儀費用が膨大にかかった、弔問客が数百人に及んだなどの事情がある場合には、弁護士基準の上限を超えて実費が認められた裁判例もあります。
死亡事故の慰謝料について弁護士に相談するメリット
死亡慰謝料の増額が期待できる
弁護士に相談すると、裁判基準である「弁護士基準」で請求できるため、慰謝料が増額される可能性があります。 通常、被害者本人やその遺族が弁護士基準で請求しても、保険会社に認めてもらうことは難しいです。 一方、弁護士が介入すると訴訟への発展を恐れた保険会社に主張を受け入れてもらいやすくなって、死亡慰謝料をはじめとした損害賠償金が、自賠責基準や任意保険基準の2~3倍に増額できる可能性が高くなります。
示談交渉を任せられる
示談交渉や加害者側とのやり取りをすべて弁護士に任せると、直接のやり取りによるストレスから解放され、遺族がすべき手続きやご自身の心の整理に集中できるようになります。 大切な家族を突然の事故で失われた方にとって、加害者側との示談交渉は想像を超える精神的な負担です。 特に死亡事故は損害賠償の金額が高額になるので、示談交渉が長期化・複雑化することも少なくありません。 示談交渉の負担を減らすためにも、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。
弁護士の粘り強い交渉により2400万円の死亡慰謝料を獲得した事例
本事案は、80歳の年金生活者が、散歩中に自動車にはねられ即死となったものです。 死亡事故特有の必要書類の取得や、慰謝料を含む損害賠償内容の精査、相手方保険会社との交渉などを任せたいとご依頼いただきました。 死亡慰謝料をめぐっては、相手方保険会社は被害者が年金を受給している高齢者であることや、同居する息子夫婦に生活を頼っていたことなどを理由に、合計1800万円以上は支払えないと強気に訴えてきました。 これに対し担当弁護士は、裁判例の検索を行い、有利となる裁判例を提示できるように準備しました。 また、依頼者はいたって健康であり、地域貢献活動を行ったり孫の成長を楽しみにしていたりした事情などを主張したのです。 その結果、被害者本人分の慰謝料として2100万円、子供2名の遺族固有の慰謝料として各150万円、合計2400万円を認めさせることに成功しました。
死亡事故の慰謝料請求は交通事故に詳しい弁護士にご相談ください
交通事故で大切なご家族を失われたことで、ご遺族は甚大な精神的苦痛を受けていることと思います。 命に代えることはできませんが、それでも加害者側からの賠償として、ご遺族には損害賠償金を受け取る権利があります。 ただし、保険会社から提示されるのは、相場よりも低い慰謝料額であることがほとんどです。 易々と応じてしまっては、保険会社の思うつぼですし、納得のいく解決とは程遠くなってしまうでしょう。 そんなとき、弁護士に依頼すれば、慰謝料を含めた損害賠償金が正当な基準で算出されるうえ、保険会社に対して交渉を進めてもらえます。 すべての手続きを任せられますので、ご心痛のなか、交渉事でさらなる負担を伴う心配もありません。 安心性や確実性、ひいては納得できる解決を叶えるためにも、弁護士への相談・依頼をご検討ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ


交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。