交通事故によるむちうち|症状・治療の注意点・慰謝料について解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故の怪我で圧倒的に多いのがむちうちです。 むちうちは事故直後には症状が出ないことがあり、外見からは症状がわかりにくく、損害賠償をめぐって事故との因果関係が争われやすいのが特徴です。 このページでは、「交通事故によるむちうち」に着目して、症状や治療の注意点など、わかりやすく解説していきます。 慰謝料の計算方法や相場といった、適正な損害賠償金を受け取るためのポイントも紹介していきますので、ぜひ最後までお目通しください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
交通事故で多い「むちうち」とは?

むちうちとは、交通事故などによって首に不自然な強い力が加わることで引き起こされる、首の捻挫などのさまざまな症状の総称です。 追突事故や予期せぬ横からの衝突、急停車などで負荷がかかる際に、首がむちのようにしなることから「むちうち」と呼ばれていますが、医師の診断書には、次のような正式な傷病名で記載されます。
- 頚椎捻挫
- 頚部挫傷
- 外傷性頚部症候群
むちうちの症状と特徴
むちうちの具体的な症状としては、次のようなものがあります。
- 肩、背中、腕の痛み
- 首、肩、背中のこり
- めまい
- 吐き気
- 耳なり
- 頭痛
- 握力低下
- 食欲不振
- 手足のしびれ
- 全身の倦怠感(だるさ)
むちうちならではの特徴・傾向がありますので、こちらもチェックしておきましょう。
- 事故直後ではなく、少し経ってから痛みなどの症状が出てくる
- 長期間にわたって症状が継続する
- 事故直後の診察では医師に「異常なし」と言われたが、調子が悪い
- 天気や湿度などにより症状が表れる
交通事故によるむちうちの治療
むちうちは事故直後には症状が出ないこともあり初診が遅れてしまいがちですので、症状を自覚した場合にはすみやかに整形外科を受診しましょう。 医師の診察だけではなく、レントゲンやMRIなどの検査も受けておくことをおすすめします。
むちうちの通院先は整形外科
むちうちの主な治療先には、整形外科と整骨院(接骨院)があります。 整形外科は、医師免許を持つ医師が治療にあたります。 これに対し整骨院は、国家資格である柔道整復師が施術にあたります。柔道整復師は医師ではないため、整骨院では診察や検査、手術といった医療行為を受けられないのが整形外科との大きな違いです。 交通事故に遭い、むちうちの症状がある場合や、特に目立った外傷がない場合などには、ひとまず整形外科を受診してください。整骨院の利用は、あくまでも医師の指示・許可のもと副次的に行うようにしましょう。
平均治療期間はどれくらい?
むちうちの平均治療期間は、一般的には1~3ヶ月程度とされています。 症状の程度や感じ方などには個人差があるため、1ヶ月かからない人もいれば、年単位で治療を行い、結局後遺症が残ってしまう人もいます。
むちうちの平均治療期間 治療期間 累積治癒率 1ヶ月以内 39.8% 2ヶ月以内 57.1% 3ヶ月以内 71.1% 4ヶ月以内 80.0% 5ヶ月以内 85.7% 6ヶ月以内 90.3%
出典:研究報告 交通事故による いわゆる“むち打ち損傷”の治療期間は長いのか(JA共済総合研究所)
治療方法
- 鎮痛剤、湿布などの処方
- ブロック注射
神経や炎症部分にピンポイントで痛み止めの注射を打ちます。 - 頚椎カラー
首を固定することで負担を和らげます。コルセットやサポーターをイメージするとわかりやすいです。 - 牽引療法
施術者や機械に首を牽引してもらうことで症状の緩和を目指します。 - 温熱療法
患部や筋肉を温めることで症状を緩和させます。 - 電気療法
こわばった筋肉が電気を流すことでほぐれ、症状を緩和させます。 - 運動療法・手技療法
施術者がもむ、たたく、おす、ふるわす、さするなど刺激を与えて痛みを和らげます。
可動域を広げる訓練や、筋肉低下を防ぐ運動を行います。
交通事故のむちうちでの注意点
症状が後から出てくる
むちうちの症状は、事故後すぐに出てくるとは限りません。 病院に行くのが遅れると、次のようなトラブルへ発展することがあります。
- 事故後すぐに病院に行かず、事故との因果関係が疑われて、損害賠償金が減額された
- 怪我人のいない「物損事故」として処理されて、慰謝料が請求できない
トラブルを防ぐためには、症状出現後は早期に病院を受診すべきです。 画像検査などを受けておくことで、事故とむちうちの因果関係を証明しやすくなります。 また、医師の診断書があれば、物損事故から人身事故へ切り替えてもらえる可能性もあります。
適切な通院頻度で通院する
むちうちの治療は、適切な通院頻度を保つことも重要です。 むちうちによる適切な通院頻度は、「週に2~3回」が一般的です。 もっとも、個々の症状によって適切な頻度は異なるため、あくまで医師の指示に従って通院することが大切です。 医師の指示に従わず、自己判断で通院を増やしたり、減らしたりすると、きちんと完治が目指せないばかりか、損害賠償請求において「過剰診療」や「治療の必要性」を疑われ、賠償金の減額・否定につながりかねません。 後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の審査に影響するおそれもあるため、医師の指示に従って、適切な頻度で通院することを心がけましょう。
後遺症がある場合は6ヶ月以上治療する
むちうちが完治せずに後遺症が残る場合には後遺障害等級の申請ができますが、認定を獲得するためには6ヶ月以上の治療期間が必要になります。 6ヶ月以上の治療期間が必要な理由として、次のようなものがあります。
- 後遺症が軽いとみなされ、後遺障害等級には該当しないと判断される
- もう少し治療を続けていれば完治したのでは、と疑われる
むちうちの治療が長引きそうな場合、まずは6ヶ月を目安に治療を継続しましょう。 そして、6ヶ月以上治療をしても完治しない場合は、後遺障害等級認定の申請をします。 ただし、6ヶ月以上の治療期間があったとしても、必ずしも後遺障害等級が認定されるわけではありませんので注意が必要です。
保険会社は3ヶ月程度で打ち切りを打診してくることが多い
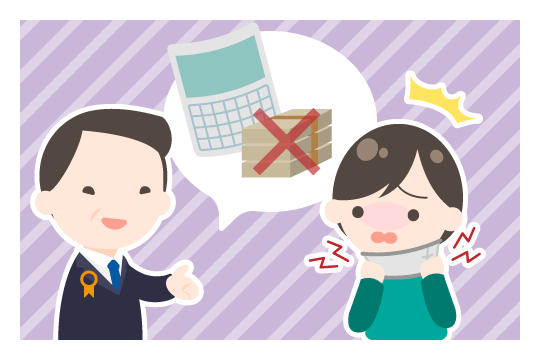
むちうちは、3ヶ月を目安に、相手方の保険会社から「治療費の打ち切り」や「症状固定」を打診されるケースが多くあります。 そもそも、治療の終了時期を最終的に判断するのは医師です。 損害賠償金にも影響することなので、保険会社から打診されたとしても、まずは医師に相談してみましょう。
治療費の打ち切りの対処法
治療費の打ち切り、症状固定の打診を受けたら、以下の対応を検討しましょう。
<治療費が打ち切られる前に>
まだ治療や通院が必要であることを伝えるなどして延長交渉を行う
<治療費が打ち切られたら>
- 自費診療を続けて、後から保険会社に治療費を請求する
- 加入している自動車保険の人身傷害保険を利用する
- 健康保険に切り替えて治療を継続し、後から負担分を保険会社に請求する
ポイントは、医師の指示に従うことです。 どうしても保険会社が応じてくれない、自分で立て替えるのは避けたいなどの場合には、弁護士に相談・依頼することで、治療費打ち切りの延長交渉をプロに代わってもらうことができます。
むちうちの治療費の打ち切りの原因となるもの
むちうちの治療費打ち切りの原因となりやすい点を押さえておくことも重要です。 例えば以下のような事情が考えられます。
- 通院頻度が極端に少ない
- 治療内容があまりにも簡易的である
- 事故の規模が小さい
- 被害者が保険会社に対して感情的であるために、診察や通院でも無理強いをしているのではないかと疑われる
いずれも客観的にみて、「そんなに治療が必要ではなさそう」と受け取れることが共通しています。 しかし、当の本人は症状に苦しんでいるのも事実です。対策として、通院時に医師に症状をきちんと伝えて必要な治療や検査を受けること、適切な通院頻度を守ること、保険会社との交渉時には冷静さを保つことなどを意識するようにしましょう。
むちうちの慰謝料など請求できるお金の内訳
交通事故によるむちうちに対して、次のような損害賠償を請求することができます。
- ①治療に関わる費用
- ②休業損害
- ③入通院慰謝料
- ④後遺障害慰謝料
- ⑤後遺障害逸失利益
具体的な内容を、次項で掘り下げてみていきましょう。
治療に関わる費用
むちうちの治療にかかった費用は、治療のために必要かつ相当な範囲内で、実費請求が可能です。 代表的なものは、次のとおりです。
- 治療費
- 入院費
- 手術費用
- 検査費用
- 投薬料
- 交通費
- 看護費
- 入院雑費
- 警察提出用診断書の作成費用 など
休業損害
休業損害とは事故で負ったむちうちの治療のために仕事を休まなければならなくなり、減ってしまった収入のことです。 この減収分は賠償請求できます。会社員のほか、自営業者やアルバイト、実質収入のない専業主婦(主夫)にも認められるのがポイントです。
入通院慰謝料
入院や通院を強いられたことで受けた肉体的・精神的苦痛に対するものです。入通院日数や治療期間によって算定されるのが基本です。
後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことで強いられる肉体的・精神的苦痛に対するものです。 むちうちが完治せずに残った後遺症が、後遺障害と認定された場合に請求することができます。 認定された等級に応じて、あらかじめ目安の金額が決まっているのが特徴です。
後遺障害逸失利益
得られるはずだった将来の収入が、後遺障害のせいで得られなくなってしまったという損害です。 むちうちの後遺症が、後遺障害と認定された場合に、将来の可能性を奪われたとして、決まった計算式を用いて算出し、賠償請求することができます。
むちうちでの入通院慰謝料の相場・計算方法
むちうちでの入通院慰謝料は、3つの算定基準のいずれかを用いて計算します。 「計算に用いる算定基準」と「入通院日数・治療期間」によって相場が異なります。
<3つの算定基準と計算方法>
自賠責基準
自賠責保険が算定に用いる基準。次の2つの計算式のうち、金額が少ない方を採用します。
①日額4300円×入通・通院のトータル期間
②日額4300円×(実際の入院・通院日数)×2倍
任意保険基準
任意保険会社が算定に用いる、独自の基準。計算方法は非公開(基本的に自賠責基準よりやや高額)
弁護士基準
弁護士による交渉や裁判所が用いる、過去の裁判例をもとに設定された基準。
通称「赤い本」に記載されている「入通院慰謝料算定表(別表Ⅱ)」を参照します。
<相場の比較>
実通院日数を月10日とした場合の入通院慰謝料の相場を自賠責基準と弁護士基準で比較してみましょう。
| 通院期間※ | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8万6000円 | 19万円 |
| 2ヶ月 | 17万2000円 | 36万円 |
| 3ヶ月 | 25万8000円 | 53万円 |
| 4ヶ月 | 34万4000円 | 67万円 |
| 5ヶ月 | 43万円 | 79万円 |
| 6ヶ月 | 51万6000円 | 89万円 |
※実通院日数を各月10日とした場合
以下のページで、むちうちでの慰謝料の相場について詳しく解説しています。 ぜひ参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
むちうちの後遺症が残った場合にすべきこと
むちうちの後遺症が残ったら、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。 後遺障害等級認定とは、むちうちが完治せず、医師に「症状固定」と診断された後も残存している後遺症が、後遺障害等級に該当するかどうかを判断してもらう手続きのことです。 後遺症の部位・程度によって、1~14級の等級が認定されたり、場合によっては非該当とされることもあります。 認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が請求できるようになります。
後遺障害等級の申請の流れ
ここで、後遺障害等級認定の申請手続きの流れを確認しておきましょう。
- ①医師により症状固定の診断を受ける
- ②医師に後遺障害診断書を作成してもらう
- ③「被害者請求」または「事前認定」により、申請を行う
- ④認定結果の通知を受ける(必要に応じて、異議申立ての手続きを行う)
※被害者請求とは、後遺障害等級の審査を行う自賠責損害調査事務所に対して、“被害者が直接”申請手続きを行うことをいいます。 ※事前認定とは、相手方保険会社が“被害者の代わりに”申請手続きを行うことをいいます。
以下のページでは、後遺障害等級認定の申請方法について特筆しています。ぜひ参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
後遺障害等級が認定されるためのポイント
むちうちは、他覚所見による証明が難しいなどの理由から、後遺障害等級認定で非該当とされることが多いのが現状です。 最低でも14級9号の認定を受けたいところですが、そのためには自覚症状を医学的に“説明”できるかどうかがポイントになってきます。
後遺障害診断書を正しく書いてもらう
後遺障害診断書は、医師に正しく作成してもらいましょう。 後遺障害等級は、基本的に書面審査で判断されます。 そのため、後遺症に至る経緯や症状の詳細が記載された後遺障害診断書が重要になるのです。
- 自覚症状の裏付けとなる、神経学的検査の結果が正しく記載されているか
- 画像検査の結果が正しく記載されているか
- 「軽減」「不変」「増悪」など、適切な表現が使われているか
- 治る可能性や改善の余地がないことがわかる内容になっているか
など、ご自身でしっかり確認し、必要に応じて医師に修正や追記を依頼しましょう。 後遺障害診断書の内容に不安がある、医師に依頼しにくいといった場合は、弁護士に依頼するのもひとつの手段です。
むちうちの症状の伝え方も重要
むちうちの場合、自覚症状の伝え方の工夫次第で等級認定の可能性を広げることができます。 同じ症状でも、伝え方ひとつで第三者の捉え方が変わり得るのです。 診察時には、ぜひ以下の点を意識して症状を伝えるようにしてみましょう。
- 一貫性
治療を続けているが改善せず、しんどいことを伝えます。天気や時間帯、日によって違うなどの発言があると一貫性に欠けてしまいます。 - 連続性
“事故直後から”症状が継続していることを伝えます。「事故からしばらくして症状が出た」「昨日は大丈夫だったけれど今日は痛い」といった発言は、連続性に欠け事故との関連性に疑いがかかってしまいます。 - 具体性
「どんな時に痛むか」「どのくらいしんどいか」など、できるだけ詳細に伝えます。
緊張したり、雰囲気に飲まれたりしてうまく伝えられないことも考えられます。 対策として、限られた診察時間内にきちんと伝えられるよう、症状のメモを持参すると安心です。
後遺障害等級と認定基準
むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級と認定基準は、下表のとおりです。
| 等級 | 認定基準 | 詳細 |
|---|---|---|
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 他覚所見がある場合に認定される可能性がある。 具体的には、レントゲン、MRIなどの画像検査結果、神経学的検査といった検査結果から「異常あり」と認めた場合。 |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 他覚所見がなく、医学的な証明は難しくても説明ができる場合に認定される可能性がある。 具体的には、事故態様や治療状況などから自覚症状の連続性・一貫性があることが認められる場合。 |
12級の認定基準にある「頑固な神経症状」とは、痛みやしびれなどのむちうちの症状が、中枢神経や末梢神経などの損傷からきていることが明らかである場合を指します。具体的には、レントゲンやMRIなどの画像で神経の損傷が確認できる状態です。 14級との違いは、この画像所見があるかないかです。12級は画像所見などでむちうちの症状を医学的に証明できる場合であるのに対し、14級は画像所見がなく自覚症状の連続性・一貫性など説明に留まる場合をいいます。
むちうちの後遺障害慰謝料の相場
| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
|---|---|---|
| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |
| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |
むちうちの後遺障害慰謝料の相場は、上表のとおりです。
認定された後遺障害等級と適用される算定基準によって異なります。
<後遺障害等級別>
むちうちで認定され得る12級と14級で比較してみると、【自賠責基準では62万円】、【弁護士基準では180万円】もの差があり、2等級違うだけでも歴然とした差があることがわかります。
<算定基準別>
【12級13号で196万円】、【14級9号で78万円】の違いがあり、弁護士基準が最も高額となることも明らかです。
後遺障害等級が認定されなかった場合の対処法
後遺障害等級が認定されなかったなど、認定結果に納得がいかない場合、次の3通りの対処法があります。
- ①異議申立て
- ②自賠責保険・共済紛争処理機構への申請
- ③裁判を起こす
3通りの対処法のうち、最も主流で確実性の高い方法が「①異議申立て」です。 むちうちの後遺症は症状が見た目ではわかりにくいことが多く、認定結果が非該当となる可能性が高いです。 そのため、被害者ご自身で自賠責保険に異議申立て(被害者請求)することで、結果を覆せる可能性があります。 異議申立てを成功させるためには、説得力のある異議申立書を作成し、セカンドオピニオンや神経学的検査の結果などの新たな証拠資料が必要です。 認定結果に納得できない方や、手続きに不安のある方は、弁護士に相談することもご検討ください。 以下のページで、後遺障害等級の異議申立てについて詳しく解説しています。 ぜひ参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
交通事故によるむちうちに関する弁護士の解決事例
等級認定サポートの結果、併合12級が認定され、約530万円で示談成立した事例
主に後遺障害等級認定のアドバイス、サポートを受けたいとの希望があり、依頼を受けた事案です。 依頼者は、バイクで信号待ちをしていたところ、自動車による追突事故に遭ったために、腰椎捻挫、肩関節打撲などを受傷しました。事故後、耳なりの症状がひどくなったため、整形外科、耳鼻科にも通院しています。おそらく、むちうちやバレリュー症候群を併発していたのでしょう。 半年ほど通院を続けた結果、耳なりや受傷部位の疼痛などの後遺症が残りました。 このタイミングでご依頼をいただき、治療経過などを確認したところ、等級認定に必要な検査を受けていないことが判明しました。即座に検査を受けていただくようアドバイスを行い、根拠となる必要書類をそろえて被害者請求にて後遺障害等級認定の申請手続きを代理しました。 その結果、耳なりや疼痛などの症状について「併合12級」の獲得に成功し、最終的に約530万円もの損害賠償金を取り付けることができました。
異議申立ての結果14級が認定され、示談額が150万円以上増額した事例
等級「非該当」の認定結果を受け、異議申立てとともに賠償金額の増額を希望され、依頼を受けた事案です。 依頼者は、信号待ちで追突事故に遭い、頚部と腰部のむちうちを受傷しました。懸命な治療を続けるも治りきらず後遺症が残ったため、後遺障害等級認定の申請を行いましたが「非該当」の通知を受けていました。なお、相手方保険会社から約89万円の賠償金の提示を受けていた状態です。 このタイミングで依頼を受けたため、まずは事故状況や治療経過の聴き取り、診断書の精査などを行いました。すると、画像所見は見られなかったものの、車両の損傷が大きいことや、約1年もの長期にわたる通院を継続していたことなどを総合的に考慮して後遺障害等級認定の余地は十分にありました。 そこで、細かい補足を行いつつ異議申立てを行ったところ、14級9号認定という結果を得ることができました。 最終的に、当初提示額よりも150万円以上増額させ、約265万円の損害賠償金を獲得することに成功しました。
交通事故後にむちうちになった場合は早めに弁護士にご相談ください
むちうちは、目に見えず、症状が多岐にわたるのが特徴です。 客観的に伝わりづらいことから「わかってもらえない」のが、症状を抱えるうえでも、示談交渉を進めていくうえでも、負担・苦痛となってくるでしょう。 交渉相手の保険会社もこの点につけ込んで、できるだけ賠償金額を抑えようとしてきます。 損をしない、泣き寝入りをしない解決を目指すためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。 弁護士に依頼すれば、適切な通院方法のアドバイスから、後遺障害等級申請のサポート、相手方保険会社との示談交渉など、すべて任せることができます。ひいては、損害賠償金の増額につながりますので、正当で満足のいく賠償を受けられる可能性が高まります。 迷いや不安、お悩みのある方は、まずは一度弁護士法人ALGにお問い合わせください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-790-073
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ


交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。










































