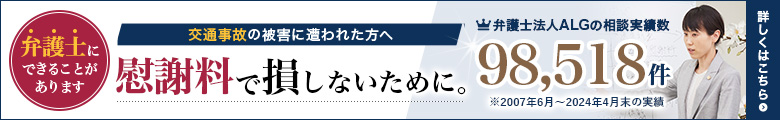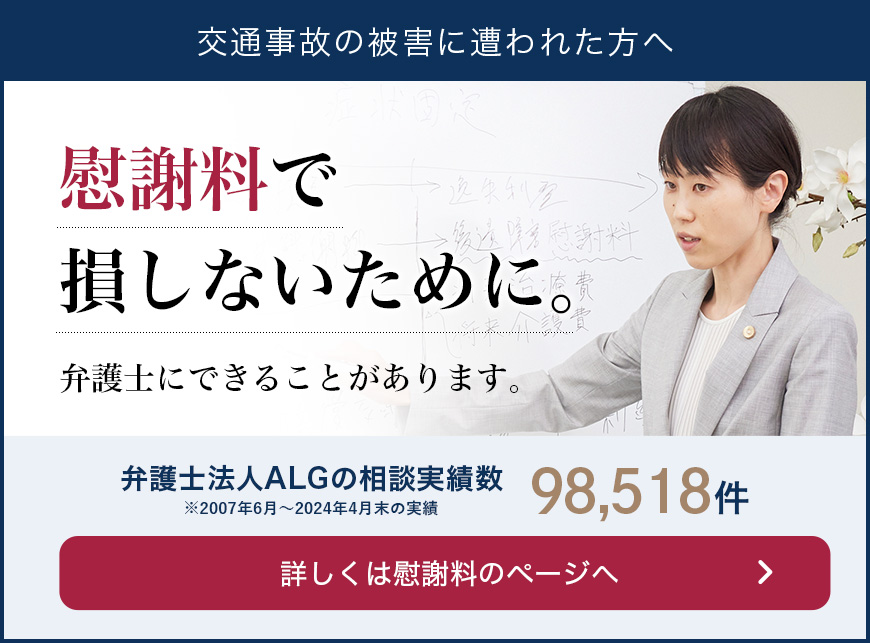交通事故で自賠責保険からは慰謝料はいくらもらえる?

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
車を運転する者なら誰もが加入する義務のある自賠責保険ですが、その補償内容を詳しくご存じの方は多くないのではないでしょうか。 交通事故の被害にあった場合、自賠責保険から慰謝料などの保険金をもらうことできますが、十分な被害弁償には足りない場合が少なくありません。 この記事では、自賠責保険の慰謝料の計算方法や請求方法などについて説明いたしますので、ぜひご一読ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
【動画で解説】交通事故で自賠責保険からは慰謝料はいくらもらえる?
自賠責保険とは?
自賠責保険は、被害者への基本的な対人賠償の確保を目的とする保険制度で、原付やバイクを含むすべての車両所有者は加入しなければなりません。未加入の場合、懲役や罰金のほか、免許停止処分となる可能性があります。
| 入通院慰謝料 | 傷害(怪我)の治療のために、入院や通院をせざるを得なくなったことで受けた精神的苦痛に対して支払われるもの |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 治療を続けても症状がなくならず、後遺障害が残ってしまったことで受けた精神的苦痛に対して支払われるもの |
| 死亡慰謝料 | 死亡によって受けた精神的苦痛に対して支払われるもの |
自賠責保険では、治療費や慰謝料(上の表をご参照ください)などの「人身損害」は補償されますが、車などの「物損」は補償されません。 交通事故の慰謝料について、さらに詳しい解説は下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
自賠責保険の入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算方法
自賠責保険の入通院慰謝料は、1日あたり4300円に、治療にかかった日数をかけて、計算します。 なお、2020年3月31日以前に起こった事故の場合は、1日あたり4200円となります。
4300円×治療日数=入通院慰謝料
治療日数は、以下の①と②を比較して、少ない方の日数となります。
① 治療期間(入院期間+通院期間)
② (実際に入院、通院した日数)×2
計算式だけではイメージがつきにくいと思いますので、具体例を用いて計算してみましょう。
例:治療期間6ヶ月、実際に通院した日数80日
治療期間は180日(1ヶ月は30日として計算します。)、実際に通院した日数は80日、180日>80日×2ですので、治療日数は160日です。よって、入通院慰謝料は4300円×160日=68万8000円となります。 2020年3月31日以前に起こった事故の場合の入通院慰謝料は4200円×160日=67万2000円となります。
自賠責保険の後遺障害慰謝料はいくらになる?
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことによる精神的・身体的な苦痛に対する補償です。その額は、以下の表のとおり、後遺障害等級に応じて決まります。
後遺障害等級とは、事故後に治療しても残った症状について、自賠責保険が認めた「後遺障害」の重さです。1級から14級まで存在し、等級が上がるほど、後遺障害慰謝料も高額になります。 「後遺障害」による損害として、ほかに逸失利益というものもあります。逸失利益とは、後遺障害が残存することにより、以前のように働けなくなることに対する補償です。 後遺障害等級が認められた場合、逸失利益と後遺障害慰謝料は各々請求することが可能となります。自賠責保険では、逸失利益と後遺障害慰謝料などの「後遺障害」による損害については、等級に応じて、合計で75万円から4000万円を上限として支払われます。 一方、「傷害」に対する保険金は、120万円を限度額として別途支払われます。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準での後遺障害慰謝料※ | |
|---|---|---|
| 別表第1 | 第1級 | 1650万円 |
| 第2級 | 1203万円 | |
| 別表第2 | 第1級 | 1150万円 |
| 第2級 | 998万円 | |
| 第3級 | 861万円 | |
| 第4級 | 737万円 | |
| 第5級 | 618万円 | |
| 第6級 | 512万円 | |
| 第7級 | 419万円 | |
| 第8級 | 331万円 | |
| 第9級 | 249万円 | |
| 第10級 | 190万円 | |
| 第11級 | 136万円 | |
| 第12級 | 94万円 | |
| 第13級 | 57万円 | |
| 第14級 | 32万円 | |
※新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
自賠責保険の死亡慰謝料はいくらになる?
自賠責基準による死亡慰謝料には、被害者本人の死亡慰謝料と、被害者の近親者固有の死亡慰謝料が想定されており、それらを合計した金額が死亡慰謝料となります。 予期せぬ事故で大切なご家族を亡くされた悲しみは、筆舌に尽くしがたいものだと思います。そのため、自賠責保険では、近親者についても慰謝料が認められています。 死亡した本人への死亡慰謝料は一律400万円※となっています。近親者固有の死亡慰謝料については、次項でご説明します 「死亡」による損害に対しては、支払い限度額3000万円の範囲内で、死亡慰謝料、逸失利益、葬祭関係費などが支払われることになります。なお、死亡までの治療費は「傷害」による保険金から支払われます。 ※新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
近親者固有の死亡慰謝料
自賠責保険の近親者固有の死亡慰謝料は、請求権者の人数によって異なります。また、被害者に被扶養者がいる場合は、200万円が加算されます。まとめると下表のとおりとなります。 なお、近親者固有の死亡慰謝料を請求できる「請求権者」になれるのは、原則、民法711条に規定された範囲の近親者、つまり被害者の父母・配偶者・子供です。ただし、事案によっては兄弟姉妹にも請求権が認められることもあります。
| 請求権者 | 近親者固有の死亡慰謝料 | 被扶養者がいる場合 |
|---|---|---|
| 1人 | 550万円 | 750万円 |
| 2人 | 650万円 | 850万円 |
| 3人以上 | 750万円 | 950万円 |
適切な慰謝料獲得のためのポイント
慰謝料の算定基準には、これまで述べてきた被害者の「基本的な対人賠償を確保」することを目的とする自賠責基準のほかにも、任意保険基準、弁護士基準という基準があります。 以下の表に各基準の内容をまとめましたので、ご確認ください。
| 任意保険基準 | 「自賠責保険では補いきれなかった損害の賠償」を目的とする、保険会社によって異なる内部基準 |
|---|---|
| 弁護士基準 | 「被害者の正当な補償」を目的とする、過去の裁判例をもとに定められた基準 |
このように、それぞれ基準の目的が異なりますので、算定される損害賠償金額にも違いが出ます。 損害賠償金額は基本的に、自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準の順で高くなります。
自賠責保険の傷害に対する損害賠償金額の限度額は120万円
自賠責保険の「傷害」に対する保険金には、120万円という支払限度額があります。 この限度額は、入通院慰謝料だけの金額ではありません。治療費や通院交通費、休業損害など、傷害(ケガ)について発生した費用は、すべての合計で120万円までしか支払われません。 そのため、治療期間が長くなって、治療費がかさんだり、休業損害などの支払いが必要となったりする場合は、120万円の枠がすぐに埋まってしまいますので、被害者のもらえる入通院慰謝料が減ってしまう可能性があり、注意が必要です。 この限度額120万円の内訳と、限度額を超えた場合の請求先について、以下で説明します。
自賠責保険の120万円の内訳
120万円の限度額には、「傷害」に係る費用がすべて含まれます。その内訳の一例をまとめたものが、下表になります。各費用の補償内容、支払基準についても記載していますので、参考にしてください。 なお、支払基準において、「実費全額」としているものがありますが、これは「“必要かつ妥当な範囲内での”実費」となります。また、カッコ書きで示している金額は、自賠責保険改正前の旧基準の金額です。改正前(令和2年4月1日より前)の交通事故には、旧基準が適用されます。
120万円を超えたらどうなる?
「傷害」に対する損害賠償金額が120万円を超えた場合はどうすればよいのでしょうか? まず、加害者が任意保険に加入している場合、基本的には、任意保険会社に対して、自賠責保険分も、その上限額120万円を超えた分も、まとめて請求すれば大丈夫です。 任意保険会社と示談交渉を行い、最終的な損害賠償金額が決まったら、任意保険会社が自賠責保険の分まで、まとめて被害者に損害賠償金の支払いを行い、後日、立替えた分を自賠責保険に請求するという方法がとられています。これを一括対応といいます。 なお、加害者が任意保険に未加入の場合は、120万円を超えた分は加害者に直接請求することになります。この場合、加害者が支払いを渋るおそれがありますので、治療費の支払いについては健康保険や労災保険などを利用して、負担を減らしておくことをおすすめします。
自賠責保険に慰謝料を請求する方法
自賠責保険に対して、慰謝料などの保険金 を請求するには、①被害者請求②加害者請求、③仮渡金請求と3つの方法があります。詳しくは、以下で説明していきます。
被害者請求
被害者請求とは、加害者側の任意保険会社を通さず、被害者が直接、自賠責保険に対して、治療費や慰謝料などの保険金を請求する方法のことをいいます。必要書類を自賠責保険に提出すると、示談成立前であっても、損害額などの調査や計算が行われ、請求後1ヶ月ほどで、自賠責保険の支払限度額の範囲内で保険金が支払われます。足りない分は加害者側の任意保険に請求することになります。 示談交渉の結果を待たず、保険金を受け取ることができますが、必要な書類を自分で用意し、手続する必要があるため、手間がかかります。 加害者が任意保険に加入していない場合や、被害者の過失割合が大きい等の理由で任意保険が病院への治療費の支払いを拒んでいるような場合などは、被害者請求を行うことを検討すべきでしょう。
加害者請求
加害者請求とは、加害者(または加害者側の任意保険会社)がまず被害者に損害賠償金を支払い、そのあとで、自賠責保険に保険金を請求することをいいます。 加害者が任意保険に加入している場合、基本的に、任意保険会社は、自社が負担する部分と本来なら自賠責保険が負担する部分をまとめて被害者に支払い、その後に立て替えた負担部分を自賠責保険に請求します。 加害者側が自賠責保険の手続きをしてくれるため、被害者にとっては手間がかからず負担は少ないです。しかし、加害者側が必要書類を集めるため、被害者に有利な証拠の収集や提出が期待しづらく、適切な保険金を受けられなくなるおそれがあります。 また、保険会社が自賠責保険に加害者請求をする際は、示談が成立していることが多いでしょう。
仮渡金制度
差し迫る治療費などの支払いに困った被害者のために、損害額がまだ確定していなくても、自賠責保険に保険金の一部を前払いしてもらうことが可能です。これを「仮渡金制度」といいます。 「仮渡金制度」には以下のような特徴があります。
- 仮渡金の金額は、傷害の場合はケガの程度に応じて5万円、20万円、40万円、死亡の場合は290万円となっている
- 自賠責保険に、事故証明書、診断書などの必要書類を提出して申請すると、1週間ほどで仮渡金を受け取ることができる
- 仮渡金請求ができるのは一回だけ
- 最終的な示談金額が仮渡金より低くなったときは差額金を返す必要がある
自賠責保険の慰謝料はいつもらえるのか
自賠責保険から慰謝料などをいつもらえるかは、請求方法によって異なります。 以下の表にまとめましたので、ご確認ください。
| 請求方法 | もらえる時期 |
|---|---|
| 加害者請求 | 示談前でも、加害者が被害者に賠償金を支払った都度請求できる。保険会社が請求するのは、基本的には示談後。 |
| 被害者請求 | 示談成立前でも可能。自賠責保険に請求後1ヶ月ほどで支払われる。 |
| 仮渡金制度 | 示談成立前でも可能。自賠責保険に請求後1週間ほどで支払われる。 |
「加害者請求」とは、加害者が被害者に賠償金を支払った後、その額の限度で自賠責保険から保険金を受け取ることができる制度です。これは被害者に賠償金を支払った加害者や保険会社が使うものです。 被害者の方は、「被害者請求」や「仮渡金制度」を使うことで、示談が成立する前であっても、慰謝料などの損害賠償金の一部となる保険金を受け取ることができます。 なかなか示談交渉がまとまらず、早めに慰謝料をもらいたいときは、「被害者請求」や「仮渡金制度」を利用することをおすすめします。
自賠責保険における過失割合の取り扱い
| 被害者の過失割合 | 傷害 | 後遺傷害・死亡 |
|---|---|---|
| 7割未満 | 過失相殺なし | 過失相殺なし |
| 7割~8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
| 8割~9割未満 | 2割減額 | 3割減額 |
| 9割~10割未満 | 2割減額 | 5割減額 |
自賠責保険では、被害者保護の観点から、被害者に重大な過失(7割以上の過失)がある場合に限って、保険金が減額されます(重過失減額)。任意保険を使う場合などには被害者の過失分だけ賠償金が減らされることがありますが(過失相殺)、自賠責保険では被害者の過失が7割未満であれば過失相殺は行われないのです。しかも、重過失減額の減額率は過失相殺よりも控えめです。 例えば、被害者の過失割合が3割で、「傷害」に対する賠償金額が120万円とします。 この場合、通常であれば、3割分の36万円が過失相殺で減額されますが、自賠責保険では、被害者の過失が7割未満であることから減額は行われません。 ただし、被害者の過失が10割の場合には自賠責保険から保険金が支払われませんので、注意が必要です。
交通事故の適正な慰謝料を受け取るためにも、自賠責保険への請求は弁護士にお任せください
自賠責保険へ被害者請求しようと思うと、準備が大変です。 また、任意保険会社に請求しても、自賠責保険の支払い基準に近い賠償額を提示されることもあります。 そこで、自賠責保険への被害者請求をお考えの方や保険会社から出された賠償提示額に不安がある方は、適切な賠償を受けるために、弁護士に依頼することをおすすめします。 弁護士に依頼すれば、被害者請求の手続きや後遺障害等級認定のサポートを受けられます。さらに、示談交渉は弁護士が行うので、ご自身の負担が軽くなるだけではなく、弁護士基準を用いることによる慰謝料増額の可能性もあります。 交通事故の被害者請求や慰謝料について不安や疑問を抱かれている方は、まずは弁護士にご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-790-073
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ


交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。