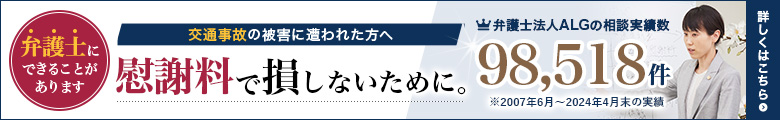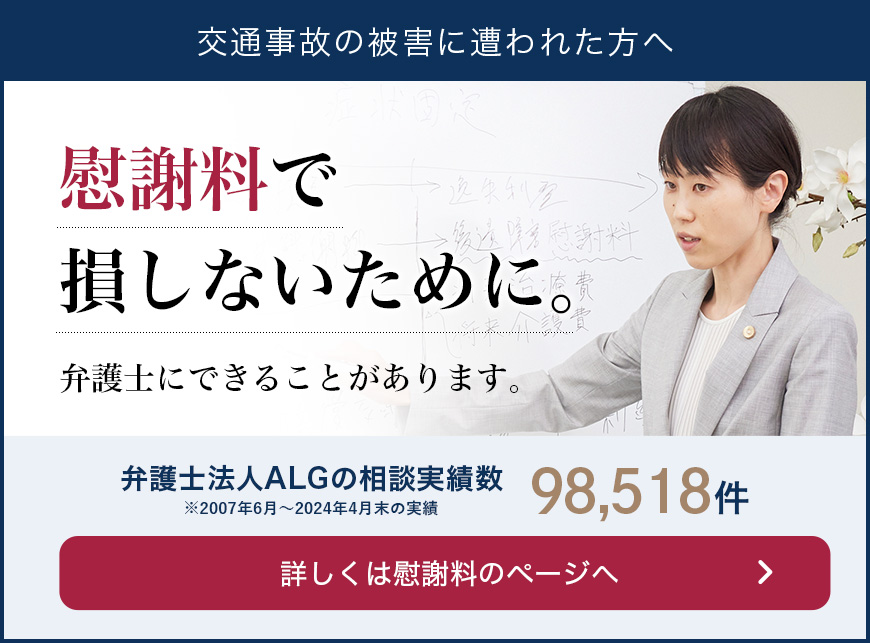車対車の事故で請求できる慰謝料|相場や過失割合について

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
この記事をご覧になっている方は、以下のような疑問を持たれてはいないでしょうか? 「車同士でぶつかり、ケガをしてしまったが、相手にどのぐらいの慰謝料を請求できるの?」 「相手方の保険会社から提示された慰謝料は正しいの?」 おそらく車同士の事故に遭われた方の多くが、気にされているポイントだと思います。 本記事では、車同士の事故の慰謝料額に影響を与える過失割合や、慰謝料の相場や計算方法などについて解説していきますので、これから示談交渉する方も、すでに示談案が提示されている方も、ぜひお目通しください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
車対車の事故で請求できる慰謝料
交通事故に遭うと大きな精神的ショックを受けます。この精神的苦痛を和らげるための賠償金のことを慰謝料といい、加害者に請求することが可能です。 車対車の事故を含め、交通事故で請求できる慰謝料は、以下3つの種類がありますので、ご確認ください。
①入通院慰謝料
事故によりケガを負い、辛い治療や手術を強いられた精神的苦痛を和らげるための補償。基本的には、通院開始から完治・症状固定までの通院期間、実際に入院、通院した日数、治療内容などに基づき、金額が決められます。
②後遺障害慰謝料
事故によりケガを負い、治療をしたにもかかわらず、後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対する補償。一般的に、症状固定後、残った後遺症について、自賠責保険の定める後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となります。
③死亡慰謝料
事故により被害者が死亡した場合の、本人及び遺族の精神的苦痛に対する補償。基本的には、遺族の人数や扶養者の有無、被害者の家族内での立場などに基づき、金額が決まります。
過失割合の基準
ケガがなく、車や所持品などが損壊しただけの物損事故の場合は、基本的には、慰謝料を請求することができません。物損事故の場合は、損害を受けた物品の補償を受けさえすれば、原状は回復されたと考えられており、別途、慰謝料も認めるべきものとは考えられていないからです。 なお、物損事故と届け出た後に、後から痛みが出てきたような場合は、早めに人身事故に切り替えることをおすすめします。人身事故として届け出ると、過失割合等を判断する際の客観証拠となりうる「実況見分調書」が作成されるからです。 事故から時間が経ちすぎると切り替えが難しくなりますので、事故発生から1~2週間以内に行うのが望ましいでしょう。 物損事故について、より詳細に知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
合わせて読みたい関連記事
車対車の事故の慰謝料額に影響する過失割合とは?
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者の責任を割合で表したものです。 交通事故では、もらい事故を除き、加害者だけに責任があるというケースは少なく、被害者にも何らかの落ち度が認められてしまうことが多いものです。被害者は、加害者に対して損害賠償金を請求することができますが、被害者にも過失がある場合は、過失割合分だけ、慰謝料などの賠償金が減額されます。 つまり、「ご自身の過失割合が多くなるほど、慰謝料などが減る」ということは覚えておくべきでしょう。
車同士の事故の過失割合は、「信号機の有無やその色」「事故の場所や時間帯」「車の進行方向」「道路の幅」「優先道路や一時停止規制の有無」「重過失の有無」などに基づき、当初は、当事者間の話し合いで決定していきます。 例えば、交差点における車対車の事故で、両車ともに赤信号だった場合の過失割合の基本は「50:50」ですが、一方が「黄信号」で、もう一方が「赤信号」と判断された場合には、「赤信号」の車の過失が80%と増えることになります。 以下の記事で、過失割合の決め方について詳細に説明していますので、ご確認ください。
合わせて読みたい関連記事
過失による減額「過失相殺」について
被害者側にも何らかの落ち度があると判断されれば、加害者から被害者に対しても、損害賠償請求が可能となります。但し、この際、請求できるのは自身の過失を相殺した額になります。 これだけではイメージしにくいと思いますので、具体例を使って見てみましょう。
例えば、「加害者の過失が8割、被害者の過失が2割、加害者の損害額が200万円、被害者の損害額が300万円」の場合、加害者が被害者に対して請求できる損害賠償金額は
200万円×(1-0.8)=40万円
となります。
次に、被害者が加害者に対して請求できる損害賠償金額は
300万円×(1-0.2)=240万円
となります。よって、被害者が最終的に受け取れる損害賠償金額は過失相殺により、
240万円-40万円=200万円
となります。
なお、過失相殺による損害賠償金の減額は、治療費や慰謝料、休業損害など、事故で被害者が受けたすべての損害が対象となります。
| 加害者 | 被害者 | |
|---|---|---|
| 過失割合 | 8割 | 2割 |
| 損害賠償額 | 200万円 | 300万円 |
| 相手に請求できる金額 | 200万円×0.2=40万円 | 300万円×0.8=240万円 |
| 実際に受け取れる金額 | 0円 | 240万円-40万円=200万円 |
もらい事故で過失0の場合の慰謝料は?
もらい事故などで被害者側に過失が全くなかった場合、過失相殺により慰謝料が減らされることはありません。 とはいえ、過失0であるからといって、適切な慰謝料額が提示されているとは限りません。 なぜなら、賠償金の支払いを抑えたい加害者側の保険会社が、任意保険基準による低額な慰謝料額を提示している可能性があるからです。 詳しくは次項でご説明します。 もらい事故の慰謝料と注意点について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
合わせて読みたい関連記事
車対車の事故の慰謝料相場と計算方法
車対車特有の慰謝料相場はなく、被害者側がバイク・自転車・歩行者であった場合でも慰謝料の計算方法は同じです。 慰謝料を計算するための基準は、以下の特徴があります。
| 自賠責基準 | 自賠責保険による支払基準で、最低補償の基準。被害者側に過失がない事故の場合は最も低額となることが多い。また、入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額がある。 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向がある。 |
| 弁護士基準 | 交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判等において使われ、被害者に過失がない場合は、最も高額となることが多い。(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載) |
- 自賠責基準≦任意保険基準≦弁護士基準の順で計算される慰謝料の金額が高くなる
- どの基準で計算するかによって、慰謝料の金額が大きく変わってくる
- 弁護士基準が基本的に最も高額になりえますが、裁判例を反映した金額であるため、最も適正な基準であるといえる
- 弁護士が代理人となって示談交渉の場に入れば、弁護士基準による慰謝料が認められる可能性がある
入通院慰謝料の相場
| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.9万円 | 軽傷19万円/重症28万円 |
| 2ヶ月 | 25.8万円 | 軽傷36万円/重症52万円 |
| 3ヶ月 | 38.7万円 | 軽傷53万円/重症73万円 |
| 4ヶ月 | 51.6万円 | 軽傷67万円/重症90万円 |
| 5ヶ月 | 64.5万円 | 軽傷79万円/重症105万円 |
| 6ヶ月 | 77.4万円 | 軽傷89万円/重症116万円 |
※2020年4月以降に発生した事故における入通院慰謝料
自賠責基準では、入通院慰謝料に①入通院期間と②実際に入通院した日数×2のいずれか小さい方をかけて計算します。 一方、弁護士基準では、入院・通院期間をもとに慰謝料の金額を決め、自賠責基準より高額になります。また、軽症と重症で金額が変わります。 入通院慰謝料の相場と計算方法について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照下さい。
合わせて読みたい関連記事
後遺障害慰謝料の相場
自賠責基準と弁護士基準による後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて、一定の基準額が定められています。 後遺障害等級とは、事故で残った後遺症について、自賠責保険を通じて後遺障害として認定を受けた等級のことです。後遺障害等級は障害の内容や重さにより1級から14級まで分けられ、1級が最も重く、14級が最も軽く、等級が重いほど、慰謝料の金額は高くなります。 以下の表はむちうちで後遺障害が残った場合の慰謝料の基準額です。むちうちで認定される可能性があるのは12級か14級です。表の金額を見比べると、自賠責基準より、弁護士基準による後遺障害慰謝料の方が高額になることがわかります。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
※( )内の金額は2020年3月31日までに発生した事故の場合
以下の記事で、後遺障害について詳しく説明していますので、ご参照ください。合わせて読みたい関連記事
死亡慰謝料の相場
| 自賠責基準 | 死亡慰謝料 |
|---|---|
| 被害者本人 | 400万円 |
| 請求者1人 | 550万円 |
| 請求者2人 | 650万円 |
| 請求者3人以上 | 750万円 |
| 被扶養者がいる場合 | 200万円 |
| 弁護士基準 | 死亡慰謝料 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2800万円 |
| 母親・配偶者 | 2500万円 |
| その他 | 2000万~2500万円 |
※2020年4月以降に発生した事故における死亡慰謝料
自賠責基準では、死亡した本人への慰謝料及び遺族への慰謝料を合計した金額が死亡慰謝料となります。死亡慰謝料を請求できる遺族は、被害者の父母(養父母)、配偶者、子(養子、胎児など含む)です。 本人への慰謝料は一律400万円、遺族の慰謝料は、請求者1人につき550万円、2人で650万円、3人以上で750万円となり、被害者に扶養されている者がいる場合には、さらに200万円が追加されます。 一方、弁護士基準による死亡慰謝料は、被害者の家庭内での立場などにより決められます。 被害者が、生計を支える一家の支柱だった場合は2800万円、母親や配偶者などは2500万円、独身の男女や子供などは2000~2500万円が一つの目安となります。 死亡慰謝料の相場について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
合わせて読みたい関連記事
車同士の事故で慰謝料が増額される要素とは?
交通事故の慰謝料は一律ではありません。同じようなケガの事案でも、ケースによって被害者が受ける精神的苦痛の度合いが異なるからです。以下のように被害者の精神的苦痛が特別に大きいと考えられるケースでは、慰謝料が増額されることもありえます。
- 加害者の運転行為が悪質な場合
加害者側にひき逃げ、飲酒運転、居眠り運転、無免許運転、著しいスピード違反などの悪質な行為があった場合 - 加害者の事故後の態度や行動が悪質な場合
事故後、被害者の救護措置を行わなかったり、一切謝罪をしなかったり、自己保全を図る発言をするなど、事故後の加害者の態度が不誠実な場合 - 被害者や親族に大きな精神的苦痛が伴う場合
事故によるケガや後遺症で仕事を失ったり、生死にかかわる大ケガをしたり、事故により大切な家族を失い、親族が精神疾患になってしまったような場合
以下の記事で、慰謝料が増額する要素について詳しく説明していますので、ご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
慰謝料以外に受け取ることができる損害賠償金
慰謝料以外にも、以下の表のような損害賠償金を請求することが可能です。
主な費目をリストアップしましたので、ご確認ください。
| 治療関係費 | 診察料、投薬料、検査料、入院費、手術費、通院交通費、入院雑費、付添看護費など |
|---|---|
| 後遺障害逸失利益 | 事故による後遺症がなければ、働いて得られたであろう将来の収入分 |
| 死亡逸失利益 | 事故によって死亡しなければ、働いて得られたはずの将来の収入分 |
| 休業損害 | 事故によるケガが原因で仕事を休んだことにより生じた収入の減少分 |
| その他 | 物損の賠償金(車の修理費など)、葬儀費用など |
各損害賠償の詳細について知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
合わせて読みたい関連記事
車同士の事故で弁護士基準以上の慰謝料の獲得できた事例
車同士の事故で、弁護士基準による慰謝料を獲得できた弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。 依頼者が停車中に後続車両から追突されるという事故が発生し、依頼者はむちうちのケガを負いました。治療終了後、相手保険会社から任意保険基準による示談金額が提示されましたが、相当低額であったため納得がいかず、ALGにご依頼されました。 担当弁護士が「入通院慰謝料については、むちうちなど軽いケガの場合、弁護士基準を用いても、骨折などの重いケガよりも低い慰謝料額になるケースが多いが、依頼者はむちうちだけでなく両脚の打撲傷も負っており、治療中の精神的苦痛も特に強いものであった」旨主張したところ、重いケガの場合と同じ、より高い基準による慰謝料の支払いを受けることで交渉が成立しました。その結果、総額として、保険会社から当初提示された金額の約2倍の賠償金を獲得することに成功しました。
車同士の事故で慰謝料請求する際は、交通事故問題に強い弁護士にご相談下さい。
車同士の事故の特徴は、「過失割合が慰謝料額を左右する」ということです。 ご自身の過失割合が高くなるほど、最終的に受け取れる賠償金額が減ってしまうため、なるべく低い過失割合で示談交渉を進めたいところです。 過失割合が高く設定されて納得がいかない方は、弁護士であれば過失割合を見直せる可能性がありますので、弁護士への相談をご検討ください。 弁護士なら、過失割合を修正するための証拠を集めたり、被害者に有利な修正要素を加えたりして、適切な過失割合を主張することが可能です。 また、弁護士に依頼すると、弁護士基準で計算した慰謝料を請求しうるため、賠償金の増額の可能性も高まります。 一人で悩まれていると余計に精神的に辛くなってしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけでも心が楽になると思いますので、一度弁護士にご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-790-073
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ


交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。