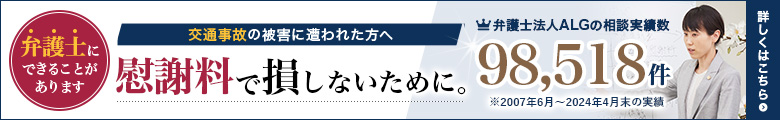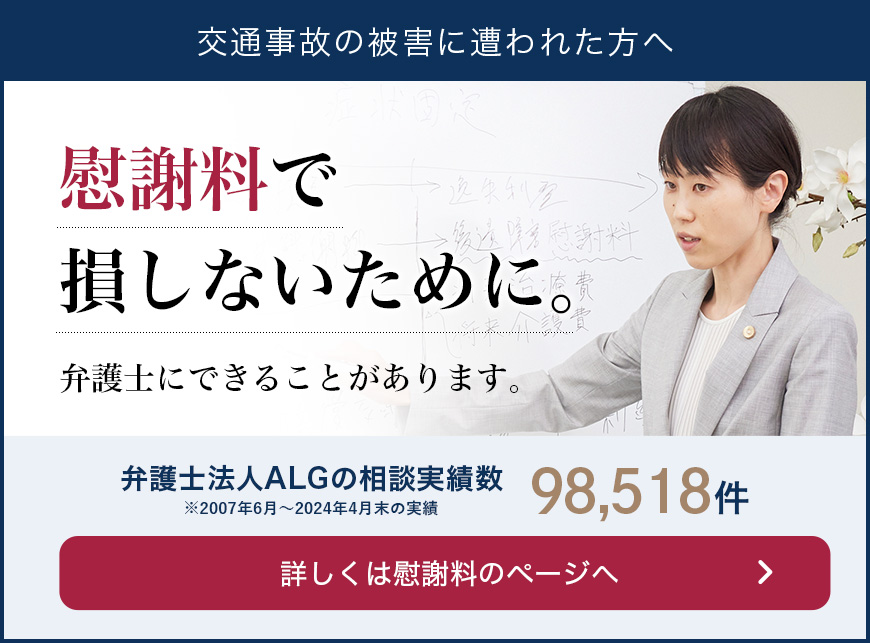交通事故で6ヶ月通院した際の慰謝料はいくら?計算方法は?

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故で負ったケガを治療するため、病院に通われている方は多いかと思います。 入通院慰謝料は、通院期間が長くなるほど増える傾向にあります。 もっとも、むちうち等の場合、通院期間が6ヶ月程度になると、相手方の保険会社から治療の終了を打診されやすい傾向にあります。 そこで、このページでは、通院6ヶ月の入通院慰謝料の目安や、保険会社から治療の終了を打診された場合の対処法などについて解説していきますので、ぜひご一読下さい。 なお、慰謝料は職業などに関係なく請求できるので、主婦であっても請求することができます。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
6ヶ月の通院期間だと慰謝料はいくらになる?相場は?
| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
|---|---|---|
| 通常の怪我の場合 | 68万8000円 | 116万円 |
| むちうちで他覚所見がない場合や軽い怪我の場合 | 68万8000円 | 89万円 |
【通院期間6ヶ月(180日)、実通院日数80日(月13日前後)、入院なし】を例に入通院慰謝料を算定すると、慰謝料の目安は上記の表のようになります。
なお、「入通院慰謝料」とは、交通事故によるケガのせいで、治療を余儀なくされた精神的苦痛に対する補償のことです。また、「実通院日数」とは、通院期間中に実際に入通院した日数のことです。 もっとも、6ヶ月の通院でも、ケガの程度、実通院日数、算定に用いる基準によって、上記の額は変化することがあります。 また、慰謝料の算定基準には、以下の3つの基準があります。
- ①自賠責基準
- ②任意保険基準
- ③弁護士基準慰謝料
このうち、弁護士基準で算定した場合が最も高額になる傾向があります。 では、入通院慰謝料の具体的な算定方法をみていきましょう。 ※任意保険基準は、任意保険会社の非公開の内部基準のため、省略しています。 3つの算定基準の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
実際の通院日数は慰謝料額にどう影響する?
まず、自賠責基準で計算する場合には、後述の計算式からすると、2日に1回の頻度で通院することが理想です。 また、弁護士基準では、基本的には、実通院日数は慰謝料の額に影響しません。もっとも、通院期間が長いにもかかわらず、通院頻度が少ない場合は、実通院日数をもとに低く算定されることがあります。 なお、不当に通院日数を増やすと、過剰診療を疑われてしまい、慰謝料や治療費が減額される可能性があります。 したがって、適切な頻度で通院を続けることが大切です。たとえば、むちうちの場合、担当医の指示に従いつつ、週2~3日、月10回程度を目安に通院するのが望ましいでしょう。
通院日数が少ない場合の慰謝料の目安等について知りたい方は、以下の記事をご覧下さい。
合わせて読みたい関連記事
通院の慰謝料額は計算方法により変わる
入通院慰謝料を計算するための算定基準として、以下の3つが挙げられます。
- ①自賠責基準
- ②任意保険基準
- ③弁護士基準
各基準の特徴を下表にまとめましたので、ご確認下さい。
| 自賠責基準 | 自賠責保険が使う基本的な対人賠償を確保するための基準。入通院慰謝料や治療費など傷害部分の保険金について120万円の支払上限額がある。 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定する基準。保険会社により内容が異なり、非公表。 |
| 弁護士基準 | 交通事故事件の裁判例をもとに作られた基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われる。 |
算定に用いる基準によって、慰謝料の額は変わります。 各基準で算定した額は、基本的には、以下のような関係になります。
自賠責基準 ≦ 任意保険基準 ≦ 弁護士基準
次項より、各基準の慰謝料計算方法を見ていきましょう。
自賠責基準による通院6ヶ月の慰謝料の計算方法
自賠責基準では、怪我の程度が重いか軽いかということとは関係なく、対象日数1日あたり4300円※となります。 対象日数は、「①入通院期間」か「②実際の治療日数(入院期間+実通院日数)の2倍」の、どちらか少ない方を採用します。 それでは、以下の例を使って、入通院慰謝料を算定してみましょう。
(例)むちうちで通院6ヶ月、実通院日数80日、入院なし
①通院期間6ヶ月=180日
②実通院日数80日×2=160日
⇒日数の少ない②を採用
したがって、自賠責基準による入通院慰謝料は、怪我の程度を問わず、「4300円×160日=68万8000円」となります。
※新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の4200円が適用されます。
弁護士基準(裁判基準)による通院6ヶ月の慰謝料の計算方法
弁護士基準では、以下の2種類の「表」を参考にして慰謝料を計算します。 2種類の表は、怪我の種類等に応じて使い分けます。
- 骨折、脱臼、他覚所見ありのむちうち等の通常のケガ→「表Ⅰ」
- 軽い打撲や捻挫、他覚所見のないむちうち等のケガ→「表Ⅱ」
下表をご覧下さい。表の入院期間と通院期間が交差する部分が入通院慰謝料の目安となります。 例えば、骨折で6ヶ月通院した場合(入院なし)の入通院慰謝料は、「表Ⅰ」を用いて、116万円となります。 また、他覚所見のないむちうちで、6ヶ月通院した場合(入院なし)の入通院慰謝料は、「表Ⅱ」を用いて、89万円となります。このように、他覚的所見のないむちうちの場合、慰謝料の目安は、骨折等の場合よりも低額になります。
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | AB | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | A’B’ | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
むちうちで通院した場合の慰謝料について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
自動計算ツールで入通院慰謝料を含む損害賠償額を確認できます
ご自身のケースでは、弁護士基準で算定すると入通院慰謝料を含めた損害賠償額はどうなるのか、知りたいと思っても、算定表の見方に困ってしまう方もいらっしゃるかと思います。 そこで、こちらの自動計算ツールを使えば、簡単な入力だけで弁護士基準の損害賠償額が確認できます。
ただ、実通院日数が少ないと入通院慰謝料が減額する場合があるように、具体的な状況によっては、自動計算ツールで確認した損害賠償額と実際の適正金額は大きく異なる可能性があります。ご自身の状況に即した、より詳しい損害賠償額を知りたいという方は、弁護士に相談することをおすすめします。
6ヶ月の通院後、治療費打ち切りと言われた場合の対処法
むちうちの場合、その程度等にもよりますが、相手方の保険会社は、事故日から3~6ヶ月程経った頃、治療の終了を打診してくる傾向があります。 しかし、本来、治療の終了時期を決めるべき者は担当医です。 この打診を鵜呑みにして、そこで治療を止めてしまうと、ケガが悪化したり、治療期間が短くなって適切な慰謝料が貰えなかったり、後遺障害等級認定の審査で不利になったりする可能性があります。 そのため、担当医から治療終了の判断がなされるまでは、保険会社から「そろそろ治療を終わりにしたら?」と言われても、必ずしも応じる必要はありません。 もっとも、保険会社が一方的に治療費の支払いを打ち切ることがあります。この場合、今後も治療を継続するのであれば、基本的には、治療費が自費になるので注意が必要です。
6ヶ月通院してもまだ治療が必要なことを訴える
相手方保険会社から治療の終了を打診されたとしても、まだ交通事故による症状が残っていて、担当医からも継続治療が必要だと言われた場合は、延長交渉を行って、治療期間を延長してもらいましょう。 延長交渉においては、以下の点が重要です。
- 交通事故直後から定期的に通院すること
- 治療の必要性を主張すること
事故直後から担当医へ詳細に自覚症状を伝えて、診断書やカルテに記載してもらい、これらの資料を保険会社に提出しましょう。 とはいえ、交渉のプロである保険会社に主張を聞き入れてもらえない場合も多いでしょう。 そのようなときは、弁護士にお任せください。弁護士であれば、専門的知識と経験をもって延長交渉することができます。 治療の打ち切りを打診された場合の対応について、さらに詳しい内容は以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
病院で治療を受ける
整骨院(接骨院)の先生は医師ではありません。整骨院では医師が行う医療行為は受けられないため、整骨院のみの通院では、保険会社に治療の必要性がないなどとみなされ、治療費を打ち切られてしまうおそれがあります。 そのような事態を回避するためには、病院をメインに通院し、治療を受けることをおすすめします。そのうえで整骨院の施術を受けたいときは、事前に病院の医師に相談し、補助的に通院した方が良いでしょう。 整骨院への通院に関する注意事項は、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
適正な頻度で通院する
保険会社に対して治療継続の必要性を主張するには、担当医の指示を仰ぎながら、適切な頻度で通院することが重要です。むちうちの場合、ケガの症状や治療の内容によって異なりますが、週2~3日、月10回程度通院するのが望ましいでしょう。 通院方法が適切であれば、治療の打ち切りを打診されても、まだ治療が必要であると反論しやすくなります。 また、適切な頻度で通院することは、後遺障害慰謝料など、入通院慰謝料以外の損害算定にも影響します。そのため、たとえ治療費が打ち切られてしまったとしても、ケガが完治または症状固定するまで、しっかりと通院治療を続けることが必要です。 治療費が打ち切られた後の通院について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
6ヶ月の通院後、「症状固定」と診断された場合の流れ
一定程度治療を続けたものの、これ以上治療しても症状の改善は見込めない場合を「症状固定」といいます。 むちうちの場合、症状固定の時期は、一般的に、事故から6ヶ月頃と言われています。もっとも、この期間は事案によって異なります。 症状固定と診断されたら、担当医に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。残った後遺症が、自賠責保険の定める後遺障害等級に該当すると認定されると、入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求できるようになります。 症状固定と言われた場合に行うべきことや後遺障害等級認定の申請手続、後遺障害逸失利益について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
むちうちで6ヶ月通院した場合のポイント
むちうちとは、事故の衝撃により、首がむちのようにしなることで起こる首の捻挫等の通称です。診断書には、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群などの傷病名で記載される場合もあります。むちうちの症状は、首の痛みや頭痛、首や肩のこり、めまいや吐き気など様々です。 むちうちの場合は、事故から3ヶ月~5ヶ月経つ頃に治療の終了を打診される場合もあります。しかし、まだ症状が残っている場合は、以下の理由から、6ヶ月は治療を続けるのが望ましいといえます。
- 痛みやしびれなどの神経症状は、ある程度の治療期間がないと改善が難しい傾向にある
- 後遺症が残った場合に申請する「後遺障害等級認定」の審査では、むちうち症で治療期間が6ヶ月未満の場合、審査上不利になる傾向がある
なお、むちうちについては、6ヶ月間治療を続けても症状が残存することが、後遺障害等級認定を受ける1つの目安とされています。そのため、むちうちによる通院が6ヶ月以上経過して、医師から症状固定の診断を受けた場合は、後遺障害等級認定の申請を行うことが望ましいでしょう。 なお、むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級は、以下のとおりです。
- 12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」
他覚的所見(MRI・CTの画像等)により、後遺症の存在を医学的に証明できること - 14級9号 「局部に神経症状を残すもの」
他覚的所見はないが、事故態様や治療の経過等により、後遺症の存在を医学的に説明できること
むちうちの症状や慰謝料の目安、後遺障害等級認定の申請方法について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
6ヶ月通院したが症状が改善せず、後遺障害等級認定をうけて慰謝料の増額に成功した解決事例
6ヶ月通院した後、後遺障害等級認定を受け、慰謝料の大幅な増額に成功した弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。
依頼者は、赤信号を無視した相手方の車に追突され、首などにケガを負い、6ヶ月の通院治療後、首の手術を受け、その後、後遺障害等級11級7号の認定を受けました。 しかし、相手方は、事故前からあった依頼者の首の既往症を理由として、30%の素因減額を主張してきたため、依頼者は納得がいかず、弊所にご依頼されました。 担当弁護士は交渉を行いましたが、相手方は主張を変えなかったので、裁判を起こしました。 裁判では、担当弁護士が相手方の主張や証拠の曖昧な部分を指摘するなどして、反論を行いました。これを受けて裁判所は、考え方を変えて、素因減額は認めないとの心証を開示しました。その結果、既払分を除き約800万円の賠償金を受けとる内容で和解が成立しました。
通院6ヶ月後の慰謝料について弁護士へご相談ください!
「事故から6ヶ月」という時期は、保険会社から治療の終了を打診されやすい時期です。 そのため、これに対する被害者の対応次第で、受け取れる損害賠償金額が大きく変わる可能性があります。 今後の対応について不安がある場合は、ぜひ弁護士にご相談下さい。 弁護士なら、適正な賠償金を受け取るための通院の仕方や、保険会社から治療の終了を打診された際の対処法について、適切にアドバイスできます。 また、保険会社との連絡窓口を弁護士に1本化できるため、精神的な負担が軽くなるというメリットもあります。 保険会社からの提案を受けた場合、ぜひ1度弁護士にご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-790-073
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ


交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。