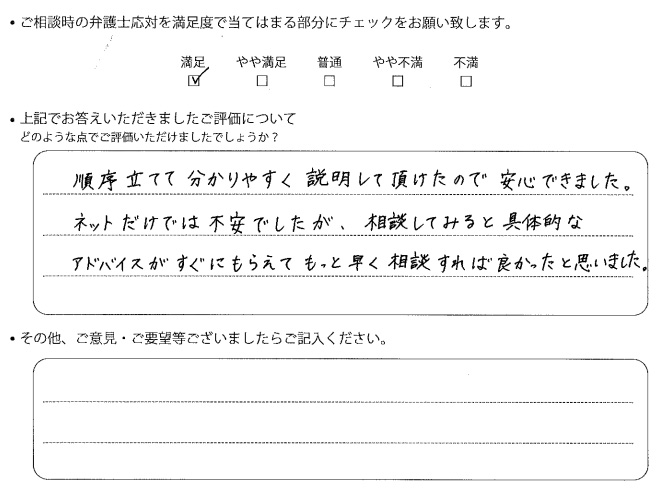交通事故で関節に可動域制限が残った場合 | 後遺障害認定について

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故により骨折や靭帯損傷になると、肩、膝、足の関節が今まで通り曲がらなくなることがあります。このような症状を「可動域制限」といいます。
一定の可動域制限が残った場合、後遺障害等級認定を受けることができます。そして、後遺障害等級認定を受けると「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を請求することができます。
この記事では「可動域制限」に着目し、可動域制限の症状や、後遺障害等級の認定について解説していきます。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
可動域制限とは
可動域制限とは、肩、肘や足などの関節の動かせる範囲が狭くなってしまうことをいいます。
可動域制限が残ると、物がうまくつかめなかったり、歩行が困難になったりします。また、股関節の可動域が制限された場合には、バランスを取りにくくなって転倒しやすくなります。
このように可動域制限は日常生活に多大な影響を及ぼします。交通事故に遭うと、一定期間治療をしても可動域制限が残ってしまう場合があります。
交通事故の後遺障害における可動域制限の原因
事故に遭って、骨折、脱臼、神経が麻痺してしまうような重大な怪我を負った場合、可動域制限の症状が現れることが多いです。
また、人工関節の挿入施術を受けたケースでも可動域制限が現れることがあります。
しかし、残存している可動域制限と事故との因果関係が認められ、後遺障害として認定されるためには、レントゲン、MRI、CTなどで実際の損傷を明らかにし、可動域制限があることを医学的に説明、証明できなければなりません。
可動域制限が起こる主な原因としては、以下の表に整理したとおりです。
| 関節の器質的変化 | 骨折後に、うまく骨がくっつかなかった場合や、通常とは異なるくっつき方をした場合、軟部組織が破壊された場合などには、可動域制限が生じることがあります。脱臼などにより軟部組織が破壊される場合も同様です。 |
|---|---|
| 神経麻痺 | 交通事故の衝撃により神経が損傷するなどして、神経が麻痺したことによって自力で関節を動かすことが困難となる場合。 |
| 人工関節 | 痛みを取り除くため人工関節を挿入置換する手術を受ける場合。 人工関節の可動域は決まっているので、これを挿入置換した場合に可動域制限が生じる場合があります。 |
可動域制限と後遺障害認定されるための要件
可動域制限で後遺障害等級が認定されるためには、①~③のいずれかに該当する必要があります。
- ①関節の「用を廃したもの」
- ②関節の「著しい機能障害」
- ③関節の「機能障害」
後遺障害等級が認定されると後遺障害慰謝料のほかに後遺障害逸失利益を請求できます。後遺障害逸失利益とは、交通事故が原因で得られなくなった将来にわたる減収に対する補償です。
後遺障害等級認定を受けるには、①~③のどれに該当するのかをしっかりと把握することが大事です。
以下の表で詳しくみていきましょう。
| ①関節の「用を廃したもの」 |
以下のいずれかに当てはまる状態をいいます。 ・関節が完全に固まって動かない状態か、それに近い状態※ ・関節が完全弛緩性麻痺で動かないか、これに近い状態※ ・人工関節や人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度と比べて2分の1以下に制限された状態 ※可動域が健側の10%程度以下の状態 |
|---|---|
| ②関節の「著しい機能障害」 | 以下のどちらかの状態をいいます。 ・可動域が健側と比べて2分の1以下に制限された状態 ・人工関節を挿入置換した関節のうち、可動域が健側と比べて2分の1以下に制限された状態以外のもの |
| ③関節の「機能障害」 | 関節の可動域が健側と比べて4分の3以下に制限された状態 |
健側とは…半身に麻痺や障害を負っている場合における障害がない側の身体を指します。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
可動域制限の程度と後遺障害等級
可動域制限の程度は後遺障害の等級に大きくかかわってきます。
後遺障害等級認定申請は治療を続けても良くも悪くもならないと判断されたとき(「症状固定」といいます。)に行います。
等級は1~14級に分類され、もっとも症状が重いものが1級となります。また、後遺障害はさらに細かく、部位や障害の性質に応じて35の系列に分類されています。
以下では可動域制限の程度と後遺障害等級の関係について、表にまとめていきます。
上肢の可動域制限と等級
ここでいう上肢(じょうし)とは、肩から指先までのことです。そのため、上肢の3大関節や手指の関節に可動域制限が残った場合、後遺障害等級が認定される可能性があります。
この場合に考えられる後遺障害等級と内容は以下のとおりです。
| 等級 | 後遺障害の内容 | 後遺障害慰謝料 (弁護士基準) |
|---|---|---|
| 1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの | 2800万円 |
| 5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの | 1400万円 |
| 6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 1180万円 |
| 8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 830万円 |
| 10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 550万円 |
| 12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 290万円 |
下肢の可動域制限と等級
ここでいう下肢(かし)とは、股関節から足の指先までのことです。そのため、下肢の3大関節や足指の関節に可動域制限が残った場合、後遺障害等級に認定される可能性があります。
この場合に考えられる後遺障害等級と内容は以下のとおりです。
| 等級 | 後遺障害の内容 | 後遺障害慰謝料 (弁護士基準) |
|---|---|---|
| 1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの | 2800万円 |
| 5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの | 1400万円 |
| 6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 1180万円 |
| 8級7号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 830万円 |
| 10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 550万円 |
| 12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 290万円 |
後遺障害認定のための可動域制限の検査方法
ただ関節に可動域制限があると主張しても、後遺障害は認定されません。
後遺障害と認定されるためには、交通事故による怪我が原因で現実に可動域制限が生じていることを、医学的に証明する必要があります。
具体的にいうと、画像診断や可動域検査といった医学的な方法により、関節の可動域制限の原因を明らかにして、確かに可動域が制限されていることを示さなければなりません。
以下、関節可動域を測定する検査方法別に説明していますのでご確認ください。
X線画像検査、CT・MRI画像検査
関節の可動域制限が後遺障害として認められるためには、機能障害の原因となる器質的損傷があることが必要です。
交通事故による、関節や関節付近の骨折や脱臼、靭帯や腱、筋肉等の軟部組織の損傷、神経の損傷といった器質的損傷は、X線やCT・MRIといった画像検査で確認できます。
できるだけ早期から継続的に画像検査を受けましょう。
可動域検査
可動域検査とは、上肢・下肢・体幹の関節がどれだけ動くのかを調べる検査です。ROM検査ともいいます。
可動域は、動かさない方の骨の軸(基本軸)と動かす方の骨の軸(移動軸)の交わるところに角度計の中心を合わせて測定します。測定は、基本肢位を0度として、通常は5度単位で行います。
体形、性別、年齢や関節構造の個人差といった諸要素が検査結果に影響する場合もあります。
関節の運動は主要運動と参考運動に分けられる
関節の運動は主要運動と参考運動に分けられ、以下の違いがあります。
- 主要運動:日常動作にとって各関節の一番重要な動き
- 参考運動:日常動作にとって主要運動ほどではないが重要な関節の動き
関節の機能障害は基本的に主要運動の可動域の制限で評価され、参考運動は基準値を「わずかに上回る」場合に用います。
各関節の主要運動と参考運動については以下表をご覧ください。
| 主要運動 | 参考運動 | |
|---|---|---|
| 肩 | 屈曲、外転・内転 | 伸展、外旋・内旋 |
| 肘 | 屈曲・伸展 | |
| 手 | 屈曲・伸展 | 橈屈、尺屈 |
| 前腕 | 回内・回外 | |
| 股 | 屈曲・伸展、外転・内転 | 外旋・内旋 |
| 膝 | 屈曲・伸展 | |
| 足 | 屈曲・伸展 |
可動域には自動運動と他動運動がある
可動域には、“自動値”と“他動値”があります。
“自動値”とは、自動運動、つまり自分で動かした場合の可動域をいい、“他動運動”とは、他動運動、つまり自分以外の外的な力で動かした場合の可動域をいいます。
そして、基本的には“他動値”によって可動域の制限の程度を評価し、等級認定を行います。ただし、麻痺により可動域が制限されているような場合には、“自動値”で評価することになります。
同一面上の運動の可動域
「同一面上の運動」とは、同じ面における関節の動きをいいます。たとえば、膝を伸ばして(伸展)戻す(屈曲)動きの場合、膝関節は前後に動くことから、前後の面における「同一面上での運動」になります。
このような「同一面の運動」には、屈曲・伸展、外転・内転、外旋・内旋、回内・回外等があります。「・」で繋がった運動はセットで検査することが多く、2つの運動の検査結果を合わせて可動域制限の程度が評価されます。たとえば膝関節の可動域検査の結果が屈曲65度、伸展0度の場合、可動域は65度となります。健側の可動域を130度とすると、この検査結果は、膝関節の可動域が2分の1に制限されているということを示しています。
通常の比較が難しい場合の参考可動域
事故前から健側となるべき側の関節に障害があったり、事故によって両側の関節に障害が残ったりした場合には、原則どおりに可動域を評価できません。このようなケースでは、測定要領が規定する参考可動域と比較することになります。
参考可動域とは、健康な人の関節の可動域を平均した値です。部位や運動の種類によって異なってきます。
各部位・運動別の具体的な参考可動域を知りたい方は、下記のページをご参照ください。
肩関節の機能障害がある依頼者について、賠償額を500万円以上増額させた事例
東京地方裁判所 平成16年12月21日判決
<事案の概要>
交通事故によって、兼業主婦である依頼者に後遺障害等級12級6号の可動域制限が残ってしまった事案です。
相手方保険会社から、既払い分を除いて約470万円という賠償案が提示されましたが、適切かどうか疑問に思われ、弊所にご相談されました。
原告の主張する後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料等について、被告が争いました。
<解決結果>
賠償案を検討したところ、特に休業損害と逸失利益の計算上、休業期間や労働能力喪失期間が短く設定されており、全体的に低額でした。
そこで、休業損害と逸失利益に関して、本件事故によって家事労働に具体的な支障が出ていること、依頼者の症状は医療記録に照らして緩解の見込みが乏しいことを説明し、弁護士基準で賠償額を見直すよう求めました。
その結果、相手方の当初の提示額から500万円以上増額させて示談を成立させることができました。
可動域制限の後遺障害が残った場合は弁護士へ
交通事故に遭って可動域制限が残ってしまうと、日常生活に多大な影響を及ぼします。そのため、後遺障害等級認定を受けることが適切な補償を受けるうえで重要です。
しかし、可動域制限の後遺障害等級認定の手続を自分で行う場合、必要書類の作成や資料の収集で多くの時間と労力を使うことになるので大変です。
可動域制限でお困りの方は交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
治療中の段階から弁護士に相談することで、後遺障害等級認定を見据えた治療のアドバイス等を受けられるので、適切な後遺障害等級認定につながります。
また、申請に必要な書類のほとんどは弁護士が集めるため、ご自身で煩雑な手続を行う必要がなくなります。
可動域制限の後遺障害等級認定でお悩みの方は、弁護士法人ALGにご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ


交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。