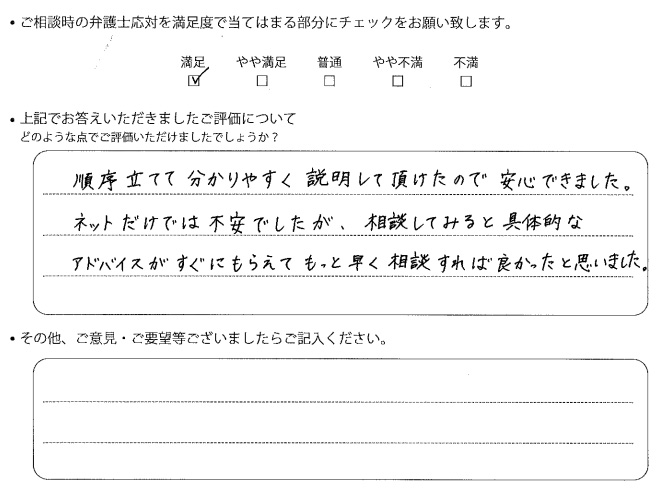遷延性意識障害(植物状態)の後遺障害と慰謝料について

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故の被害者が遷延性意識障害になり、目覚めなくなってしまったといった状況になれば、ご家族の方にかかる精神的・身体的負担や経済的負担は計り知れません。
被害者・ご家族ともに、交通事故による心身へのダメージを完全に拭い去ることは難しいでしょう。そこでまずは、経済面における負担を軽減できるよう、適切な損害賠償を受けるべきといえます。
本ページでは、ご家族が遷延性意識障害になり悩まれている方、またご不安な気持ちがある方のためとなり、参考となるような情報を詳しく記載しています。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
遷延性意識障害とは
遷延性意識障害とは、昏睡状態に陥って他人と意思疎通ができなくなる障害であり、いわゆる「寝たきり(植物状態)」のことをいいます。
脳死と混同されることがありますが、脳死とは異なり、生命維持に必要な脳幹や中枢神経系、臓器が正常に機能しており、意識回復の可能性があります。
遷延性意識障害は、以下の6要件を継続して3ヶ月間満たすことで診断されます。
- 自力移動不可能
- 自力摂食不可能
- 尿失禁状態にある
- 声は出せても意味のある発語は不可能
- 「眼を開け」「手を握れ」等の簡単な命令にはかろうじて応じられることもあるが、それ以上の意思疎通が不可能
- 眼球はかろうじて物を追えても認識は不可能
日本脳神経外科学会植物状態患者研究協議会「植物状態の定義」(1972年)
遷延性意識障害の原因と治療法
「遷延性意識障害」は、頭部に強い衝撃を受けたことによる脳挫傷(脳の打撲)やびまん性軸索損傷(脳神経細胞の断裂等)といった脳損傷により、脳が広範囲にわたって壊死または損傷することによって起こります。
しかし、現在の医療技術では有効な治療方法が確立されていません。
そのため、基本的な治療方針は、現状維持を図り、被害者自身の自己治癒力による回復を待つしかありません。
なお、ご家族の献身的な介護や、脊椎電気刺激療法、脳深層部刺激療法、音楽運動療法などにより回復が見られたケースもあります。 しかし、最小意識状態(物を目で追う、声かけにまばたきで反応するなど)や高次脳機能障害(記憶障害、失語症など)までの回復にとどまることが多く、完治は大変難しいといわれています。
遷延性意識障害の症状固定
医学的には、意識不明の状態が3ヶ月継続することで遷延性意識障害を診断できるので、3ヶ月経過した時点で症状固定を診断できるといえます。 もっとも、意識不明に陥った初期の段階では、治療やリハビリによって意識レベルの改善がみられることも多いため、症状固定は慎重に診断されます。具体的には、1年~1年半にわたって、上記の6要件を満たすとき遷延性意識障害と診断され得ます。
遷延性意識障害の後遺障害等級と慰謝料
遷延性意識障害となった場合、痰の吸引や酸素の吸入、床ずれの防止など24時間体制の常時介護が必要となります。 そのため、遷延性意識障害となった場合には、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として1級1号(別表1)の認定がされます。これは、すべての後遺障害等級の中で最も重いものであり、慰謝料等の損害賠償額も高額となります。
請求できる後遺障害慰謝料
遷延性意識障害を患った場合は、最も重い1級1号という後遺障害等級が認められ得るとご説明しました。額としては以下のとおりです。
| 等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級1号(別表1) | 1650万円 | 2800万円 |
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
後遺障害慰謝料以外に請求できるもの
遷延性意識障害が後遺障害として認定された場合、後遺障害慰謝料以外にも、様々な項目の請求が認められ得ます。
例えば、積極損害(交通事故が原因で出費せざるを得なかった損害)や消極損害(交通事故に遭わなければ得られていたであろう利益についての損害)に対する賠償を請求することができます。
以下、考えられるものをリストアップしましたのでご覧ください。
入通院慰謝料
通院や入院を余儀なくされた場合、心身へ苦痛は避けられません。入通院慰謝料は、そのような苦痛に向けて支払われます。特に、遷延性意識障害は、多くの場合長期間の入院が必要になります。そのため、入通院にかかる慰謝料の金額も大きくなる可能性が高いでしょう。
治療費
治療によっても改善が見込めないと判断されるまでに発生した、診察や検査のための費用、入院や手術をした場合の費用、さらには投薬の費用などに要したあらゆる費用は、原則として、請求可能な範囲に含まれます。
付添看護費
遷延性意識障害では長期にわたる入院が必要になりますが、医師の指示により付き添いが必要とされた場合には、付添看護費を請求することができます。日額6500円(職業付添人の場合には実費)を基準に計算されます。
自宅改造費・車改造費・引っ越し費用
介護しやすいよう、自宅や車を改造したり、より介護に適した住居に引っ越したりした場合には、必要かつ社会通念上相当な範囲であれば、自宅や車の改造費、引っ越し費用が認められます。
将来介護費
将来にわたって24時間常時の介護が必要となるため、将来の介護費用を請求することができます。症状固定時から平均余命までの期間を目安に、日額8000円~20000円(職業介護人の場合には実費)を基準として計算されます。
(介護)雑費
介護を行うには、おむつや導尿のためのカテーテル等の物品が必要です。 介護に取りかかる前や介護途中での整備には費用もかさみますが、当該交通事故に起因し、補償すべき損害と一般的に判断できるため、介護雑費の請求も認められています。
交通費
被害者が入通院中に、家族などが病院に付き添いのために赴いた際にかかった交通費はもちろん、在宅介護となった場合の通院の付き添いのために発生した交通費も、基本的に、請求可能です。
しかし、移動手段によって異なります。例えば、電車やバスなど公共交通機関で移動した場合は、基本的に、全額受け取ることができます。一方、タクシーで通院した際の代金は、ケガの症状や程度などを考慮し、必要性によって支払いの可否が判断されます。 また、自家用車で病院へ向かったときは、実際にかかった駐車場料金と、ガソリン代(15円/1㎞)などが支払われます。
休業損害・逸失利益
休業損害や逸失利益について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
合わせて読みたい関連記事
成年後見人申立ての必要性について
遷延性意識障害の被害者は、判断能力を失っているため、加害者側との示談交渉も、損害賠償請求も行うことができません。
そのため、家庭裁判所に「成年後見人」の選任の申立てを行い、本人に代わって意思表示ができる成年後見人の選任をしてもらうことが必要になります。
成年後見人とは、精神上の障害によって判断能力が不十分な方が不利益を受けないよう、本人に代わって必要な契約を締結したり、財産管理をしたりする代理人のことをいいます。
通常、家族や親族が成年後見人になりますが、示談交渉や裁判の可能性などを考えると、弁護士に成年後見人になってもらうと安心です。 なお、被害者が未成年の場合は、親権者がすでに法定代理権を持っており、本人に代わって意思表示等ができるため、成年後見人の選任は必要ありません。
また、成年後見費用は損害賠償の項目に含めることが可能です。成年後見開始審判の申立費用や弁護士などの成年後見人に支払った報酬金も、加害者側に請求できます。
保険会社との示談における注意点
平均余命が短いことを理由に減額を求められたら
遷延性意識障害になってしまった場合、将来にわたって必要となる介護費用や逸失利益も請求することが可能です。
被害者が生きている限り必要となる費用であるため、余命の長さが、金額に影響を及ばします。
遷延性意識障害の患者の平均余命は短い傾向にあり、およそ3年程度であると言われています。
そのため、賠償金の減額を図りたい加害者側の保険会社から、将来の介護費用や逸失利益について減額を求められる可能性があります。
しかし、裁判所など実務上では、一般的に平均余命で賠償額が計算されていますので、保険会社からの提示に安易に応じてはいけません。余命について争いになった場合は、弁護士への相談をご検討ください。
在宅介護は認められないと言われたら
遷延性意識障害の場合、医師より症状固定と判断された後は、入院を続けることが難しくなり、転院を促されるケースが多くなっています。ご家族は仕方なく、在宅での介護か、施設に入所するか、どちらかの選択を迫られることになります。
ここで問題になるのが、将来介護費です。将来介護費は在宅介護か施設介護かによって、金額に大きな差が出るからです。
在宅介護の場合は、訪問介護費用のほかに、家族による介護費用、自宅のバリアフリー化費用なども請求できるため、施設介護よりも高額になる傾向があり、1億円を超える賠償額を認める裁判例も出ています。
在宅介護は補償額でメリットがあるものの、24時間常時の介護が求められ、痰の吸引や酸素吸入なども行う必要があるため、ご家族の負担が大きいというデメリットがあります。どちらを選ぶかは、ご家族の判断となります。
なお、在宅介護を選択した場合、賠償額を抑えたい保険会社から、在宅介護による賠償金請求を拒否されるおそれがあります。この場合は、弁護士の力を借りることをおすすめします。弁護士であれば、自宅介護の必要性を立証するために尽力することが可能です。
交通事故による遷延性意識障害の裁判例
【大阪地方裁判所 令和2年3月31日判決】
事案の概要
交差点において被害者(当時15歳)運転の自転車と、加害者運転の自動車とが出会い頭に衝突したという事故でした。被害者は事故により、硬膜下血腫や脳挫傷などの傷害を負い、遷延性意識障害の状態となってしまいました。後遺障害1級1号として認められた後、被害者とその家族が、加害者に対して損害賠償金の支払いを求めた事案です。
裁判所の判断
裁判所は、相談支援センター作成の介護計画案(身体介護や訪問入浴などの回数など)や介護給付費明細表(介護の単価など)にもとづき、後遺障害の状況なども考慮し、事故と関連性のある、将来の職業介護人による介護費用を「1ヶ月48万円×12ヶ月×16.3056(被害者の平均余命等に基づくライプニッツ係数)」で計算し、約9392万円と認定しました。
さらに、被害者の介護については、家族による介護も必要であるとし、職業介護人による介護で、家族の負担はある程度軽くなることを踏まえ、日額5000円が相当と判断しました。その結果、将来の家族による介護費用を「日額5000円×365日×16.3056」で計算し、約2975万と認めました。
これ以外にも、後遺障害慰謝料2800万円、逸失利益9054万円と認められ、合計して約1億2818万円(過失相殺前2億4221万円)の賠償金の支払いが加害者に命ぜられました。
交通事故で遷延性意識障害になってしまったら弁護士にご相談ください
遷延性意識障害の場合、被害者ご家族にとって、24時間、365日、気の許せない介護が続くことになるため、そのご負担は計り知れません。せめて、十分な賠償金を受け取って、経済的な負担だけでも軽くしておきたいところだと思います。
しかし、保険会社は賠償額が高額になるので、「平均余命が短いから、将来介護費は少なくなるはず」などと言って、適正額より大幅に下回る提示をしてくるケースが少なくありません。
賠償金請求についてお困りの場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、後遺障害認定のための書面の作成や手続き、保険会社との示談交渉など代行して行い、ご家族が介護に専念できるよう、全力でサポートすることが可能です。その結果、適切な賠償金を得られる可能性も高まります。
ご家族の負担を少しでも軽くする手助けをさせていただきますので、ぜひ、弁護士法人ALGにご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ


交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。